休日の午後、僕は人気のない公園を散歩していた。
公園の隅にある古びたベンチに腰を下ろそうとしたその時、視界の端に赤い革表紙の日記が入ってきた。その日記には、飾りもタイトルもなく、ただ中央に黒い字で『開くな』と書かれている。
「開くなって書かれると、余計に開きたくなるよな」
カリギュラ効果ってやつだ。好奇心が勝り、僕はそっとその日記を拾い上げ、ページをめくった。
最初の数ページはただの文字の羅列だった。
「なんだ? これ?」
意味を持たない暗号か、もしくは誰かのいたずら書きだろうと思い、ページをさらに進めた。
だが最後のページをめくった途端、背筋に奇妙な感覚が走った。
『やっと気づいてくれた』
まるで日記そのものから響いてくるかのような、囁く声。
驚いて周囲を見渡したが、公園には人影ひとつない。
心臓が早鐘を打ち始める。
幻聴か?
いや、それにしてはあまりにも鮮明だった。
『頼む、僕を助けてくれ』
その声は再び響いた。僕は震える手で日記を閉じ、ベンチに置いて立ち去ろうとした。 ――だが、身体は動かなかった。
『行かないで。君しかいないんだ』
声には悲痛さが滲んでいる。
「君は誰だ?」
僕は声に出して尋ねた。馬鹿げているとは分かっていたが、黙っていることができなかった。
『僕は、この日記の持ち主だった。でも、今はこの中に閉じ込められている』
その声は静かで、どこか哀しげだった。
「閉じ込められているって、どういうことだ?」
『日記を書くたびに、自分の感情が日記に吸い取られてしまったんだ。最初は何も変わらなかった。でも気づいたときにはすでに、僕自身がこの日記に囚われてしまったんだ』
声は、ひどく疲れているように感じられた。
僕は混乱しつつも好奇心を抑えきれず尋ねた。
「それで、どうやって君を助ければいいんだ?」
『君がこの日記に、何かを書き込めば、僕は解放される』
僕はためらった。
本当にそんなことが起こるのか? これは罠ではないのか?
それでも、あまりに切実なその声を無視することはできなかった。
僕は日記を開き、最初の空白のページにペンを走らせた。
『君は自由になる』
その瞬間、指先から身体全体に不思議な感覚が広がった。それと同時に、僕の頭の中には知らない記憶が流れ込んできた。それは見知らぬ男が過ごした人生の一部だった。まさに他人の日記の中に飛び込んだような感覚だ。
日記から声が再び響いた。
『ありがとう。でも、ごめん。さっきも言ったけど、この日記に文字を書いた者が、この日記に囚われることになっているんだ』
「えっ?」
気がつくと、僕の視界は狭まり、手足の感覚がなくなっていく。身体が抗いがたい強い力で、どこかへ吸い込まれていくような感覚がした。
目を開けると、僕はもう、どこか別の空間にいた。
狭く閉じられた場所だった。暗闇の中にぼんやりと光る文字が浮かんでいる。
『君は自由になる』
僕が書いた言葉だった。
ここからどれだけ叫んでも、誰にも届かない。僕は完全に日記の中に閉じ込められてしまったのだ。
外の世界では、元の日記の持ち主が僕の身体を借りて、ゆっくりと立ち上がっていた。
「悪いね。でも、これが唯一の方法だったんだ」
そう言って彼は、再び赤い日記をベンチの上に置いて立ち去った。
僕は絶望しながら、暗闇の中で祈った。いつか誰かがまた、この日記を手に取り、ページをめくってくれることを。
『開くな』
今になってようやく、それが罠だったことに気づいた。だが、それはもう手遅れだった。



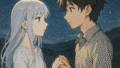
コメント