「信じてもらえないかもしれないけど、このバーに幽霊がいるって知ってるか?」
隣の席の男が唐突に話しかけてきた。その夜、僕はいつものように馴染みのバーで一人、静かな時間を楽しんでいた。彼の声は静かな店内にしっくりと馴染み、不思議な雰囲気を作り出していた。
「幽霊……ですか?」
僕は思わず返事をしてしまう。男は酔っているのか、鼻が赤く目の焦点も合わないようだった。だが、表情は真剣だ。
「そうだよ。信じなくてもいい。でもね、カウンターの端っこ、あの席にいつもいるんだよ。もう黙っていられなくて」
男が指差したのは、入り口に近いカウンターの端。たいていは空いているその席には、もちろん誰もいない。
「いつも一人で飲んでる男がいてさ、話しかけても返事もしない。でも、なぜか気になってしょうがないんだよ」
男の声には妙に切実な響きがあった。僕は苦笑いしながらも、その席を何気なく見る。――もちろん誰もいない。
しかし、その瞬間、確かに何かが揺らいだような気がした。まるで誰かがそこに座っていて、「私のことですか?」と振り返ったように――。
次の日の夜、僕は再びそのバーを訪れた。カウンターの端の席がまた空いている。その席に視線を向けると、今度は違和感がはっきりと感じられた。まるで陽炎のように空間が揺らいで見える。
バーテンダーが僕の様子に気づき、そっと声をかけた。
「どうかしました?」
「いえ、実は昨夜、その、隅の席に幽霊がいるって聞いたんですよ。――まぁ、その人、だいぶ酔っ払ってましたけどね」
バーテンダーは微かに笑みを浮かべながらうなずいた。
「それ、実は結構有名な話なんですよ」
店主自身がその話を面白がるように語るのは意外だった。業務妨害だと怒られるかと思った。
「昔、毎晩来ては静かに一杯だけ飲んで帰るお客さんがいたんです。『一杯だけだから隅っこでいいよ』なんてね、その隅の席に座る。謙虚で好感のもてる方でした。しかしある晩を境にぱったり来なくなってしまったんですよ」
バーテンダーの視線はカウンターの端に向かっている。
「その辺りから不思議なことが起きるようになりました。閉店後にグラスを片付けても、翌朝、必ずあの席にだけ使った形跡があるグラスが残されているんです」
ゾッとしたような、不思議な感覚に襲われた。気づくと僕は思わず口にしていた。
「それで、彼が何かを伝えたいんでしょうか?」
バーテンダーは静かに肩をすくめた。
「僕にも分かりません。ただ、怖いとは感じないんです。寂しそうで、少しだけ温かい感じがして……いつも通りその席で飲んでいるだけでしょう」
僕はその夜、思い切って例の席に座ってみた。店内は静かで、いつもと変わらない穏やかな空気が漂っている。
ふと、目を閉じる。すると、不思議なことに、耳元で囁くような声が聞こえた気がした。
「君も一人か?」
目を開けると、目の前には透明な人影があった。中年の男性で、穏やかな表情を浮かべている。悲しいわけでもなく、怒っているわけでもない。ただ、少しだけ寂しそうだった。
「あなたが、このバーにいるという噂の幽霊……さんですか?」
僕の問いかけに、彼は静かに頷いた。
「ここが好きでね。ここにいると――とても落ち着くんだ」
僕は思わず頷いた。彼に怖さは感じなかった。むしろ、寂しげで切ない存在に思えた。
「どうして、ここを離れないんですか?」
「約束したんだよ、誰かとまたここで会うって」
「誰と?」
彼は微笑んで、言った。
「ずいぶん前に会った若い女性だ。彼女はここで働いていた。でも、ある日急にいなくなった。きっといつか戻ると思って、毎日ここで待っているうちに……」
「彼女は戻ってこなかったんですか?」
彼は寂しそうにうなずいた。
「でもね、不思議なことに、ここで待っていると、いろんな人が話しかけてくれる。それが嬉しくてね、ここに留まってしまったんだ」
彼の表情に悲壮感はなかった。ただ、静かな満足感があるように見えた。
やがて、人影は徐々に薄くなり、気づくと完全に消えていた。目の前には空になったグラスだけが残っている。
後日、再びバーを訪れると、バーテンダーが微笑みながら話しかけてきた。
「昨晩、何かありましたか? そこに座ってらっしゃったようですけど――。今朝、あの席にグラスが残っていなかったんですよ」
僕は笑ってうなずいた。
「ええ、少しだけ、話をしました」
バーテンダーはホッとしたような笑顔でうなずいた。
「あの人、ようやく満足したのかもしれませんね」
今でも、たまにカウンターの端を見つめる。そこにあの幽霊がいる気配はないが、ふとした瞬間、温かな気配を感じることがある。きっと彼は、次の場所へ旅立ったのだろう。
それとも、どこかのバーのカウンターで、また誰かに話しかけてもらうのを待っているのかもしれない。

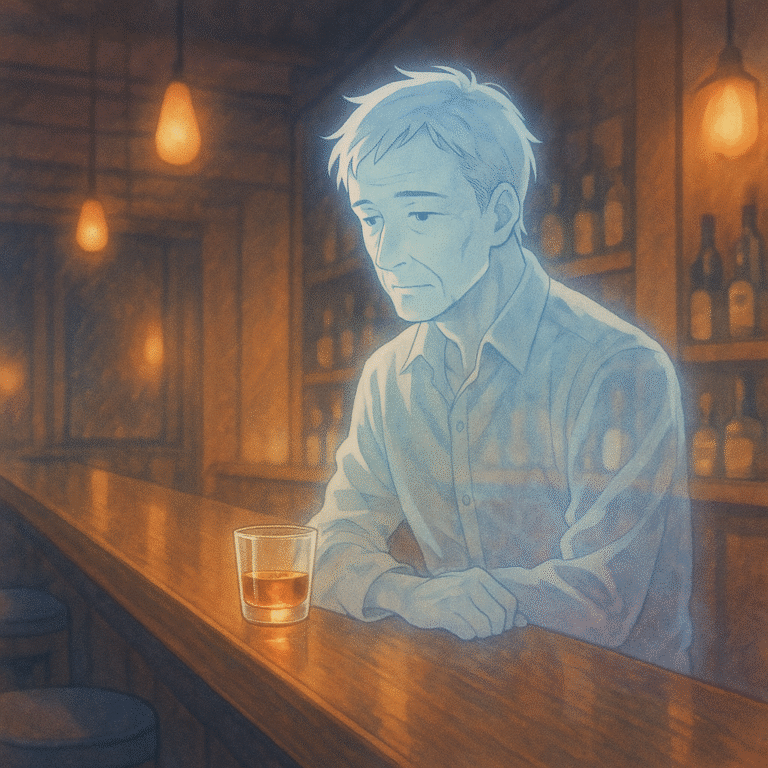


コメント