「会社の近くの大きい交差点、あの信号機の上さ、知ってるか? 夜になると、何かがいるんだよ。じっと交差点を見下ろしてる“あいつ”がさ」
今思えば、同僚にそう言われて、そこを確認したことがすべての元凶だった。
深夜の交差点は不気味なほど静かだ。その日も終電を逃して歩いていたのだが、いつもの交差点に差し掛かったとき、同僚の言葉をふっと思い出した。
確か……信号機の上。
見上げた瞬間、心臓が止まるかと思ったよ。そこにいたんだ。“何か”が。
影みたいに黒くて、長い腕と脚をぐにゃぐにゃさせながら、信号機の上にしゃがんでた。顔は見えない。ただ、確かにこっちを見てたんだ。
立ち去ろうとしたが、足がすくんで動けなかった。
するとそいつが口を開いた。声が耳に直接響く感じでさ、耳障りな声でこんなことを言ったんだ。
「お前、今、ここを渡るつもりか?」
その声に全身が冷たくなった。渡ろうと思っていたが、こんなのがいるなら渡りたくない。
「いや……」と答えると、そいつはクククと喉の奥で笑った。
「ならいい。渡ればどうなるか――それは明日のお楽しみ」
恐ろしくなり、とにかく来た道を走って逃げた。
翌朝、同じ交差点に差し掛かったとき、僕は思わず足を止めて信号を見上げた。
信号機の上には何もいない。
昼間の交差点は普通に人が行き交っていて、昨夜のことなんて嘘みたいだ。でも、昨夜の声が耳に残って離れなかった。
その晩、やめておけばいいのに、どうしても気になってしまい、僕は交差点に行った。昼間の様子から昨夜のあれは夢だったような気もしていた。確認しないと気持ち悪くて仕方ない。
しかし、信号機の上にやはりあれがいた。
「今日は渡るか?」
不愉快な声がまた響く。僕は息を整えて問い返した。
「渡ったら何が起こるんだ?」
「変わる。お前の運命がな。どう変わるかは、お楽しみ」
そいつは喉の奥でまたクククと笑った。僕は迷った。なぜか好奇心を抑えきれなかった。無視して引き返せばいいのに、気づいたときには交差点に足を踏み出し、渡り始めていた。
すると、突然あたりが静まり返った。
風の音も、車の音も完全に消え、世界が時間を止めたみたいに固まった。
周りを見ると、人も車もピクリとも動かない。驚いて振り返ると、月に照らされたあの信号機の影が僕のすぐ隣まで伸びていた。
信号機の上からアレが僕の一挙手一投足をじっと見守っている気配に耐えられなかった。僕は踵を返して、元来た道を駆け戻る。
「おやおや、どうしたんだい?」
そいつはケタケタと笑う。
「ここを渡ったら何が起こるんだ?」
「交差点を渡った者は、別の世界に踏み込むことになる。お前たちの呼び方をするならそれは『死』だ。お前はもうこの運命から逃れられない」
「まだ渡ってないぞ?」
「いいや、いつか渡るさ。お前は渡る。昨夜も今夜もここに来たのはなぜだ?」
僕はハッとした。「どうしても気になって」、「好奇心から」、言い方はいくらでもあるが、確かに来なければいいだけなのに、自分を抑えることができなかった。
絶望する僕にそれは小さな声で囁いた。
「嫌なら別の誰かをここに連れてこい。簡単なことだ。会社でも家でも、何なら聞こえよがしにひとりごとを言ってもいい。『あそこの交差点の信号を夜に見上げてみろ。何かがいるぞ』と言えば誰かが引っかかるぞ」
信じられなかった。つまり自分は同僚に引っかけられたのだ。悪魔みたいな提案じゃないか。
「そうしたら、どうなるんだ?」
「お前は二度と俺を見ることはない。別の誰かが、そのうちこの交差点を渡って――あとはお楽しみ」
翌日僕は満員のバスの中で携帯電話を取り出した。
「ああ。そうだ。あの交差点。知ってるだろ。その信号機の上に本当にいたんだよ。変なのがさ」
周りは迷惑そうな顔をしてこちらを見ている。もちろん携帯電話はどこにもつながっていない。何もないひとりごとを言う勇気はなかったので、電話をしているふりをしている。
「いいから、一度見てみろって。夜だけだぞ。僕もただのイタズラだと思ったんだけど――」
何人かが僕の声をじっと聞いている気配がする。気にならないわけがない。この中の誰かが必ずあの交差点に行くだろう。
僕はさりげなく交差点の場所を特定できるような情報を話し、携帯電話を鞄にしまった。
数日後の夜、あの交差点の信号機の上を見上げたが、そこには何もいなかった。



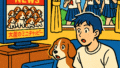
コメント