あれは高校二年の夏の合宿でのことだった。
うちのバスケ部は毎年、校内合宿をしていて、その日は夜遅くまで体育館で練習していたんだ。
ようやく練習が終わり、片付けをしているときだった。静まり返った校舎の方から、奇妙な音が聞こえてきた。
「……ん?」
耳を澄ますと、はっきりと聞こえる。誰かの笑い声だ。
それがまた不気味なことに、やけに陽気な笑い声だった。
「おい、アレ、聞こえるか?」
最初に口を開いたのは、後輩のタケシだった。
「ああ、聞こえるな……どこだろ?」
俺が答えると、部長のヒロキが小さく震える声で言った。
「屋上から……じゃないか?」
その瞬間、俺たちは顔を見合わせた。無視すべきだったのかもしれない。だが、誰もが合宿という状況の高揚感のせいか、好奇心の方が勝ってしまったんだ。
「屋上で何かやってるんじゃないか。ちょっと見に行こうぜ」
俺の提案に、全員がなんとなく頷いた。
階段を上がり始めると、空気が急に重く感じられた。意気揚々と体育館を飛び出した俺たちだったが、自然と口数が減っていく。校舎内は真っ暗で、階段の電気も切れているらしく、スマホのライトを頼りに登っていった。
それでも、屋上からは楽しげな笑い声がはっきりと聞こえ続けていた。
「なんか変だな……」
タケシがぼそりと呟く。ヒロキが慌てて口を挟んだ。
「そういうこと言うなよ、怖くなるだろ」
ヒロキは普段クールで強気なタイプだが、今日ばかりは明らかに動揺しているようだった。
ようやく屋上の扉にたどり着き、俺がゆっくりドアノブを回す。
ギィィィ……
重たい扉が軋んで開く音が、やけに大きく響いた。その瞬間、さっきまでの笑い声がピタリと止んだ。
俺たちは一斉に屋上へ飛び出した。
だが、そこには誰もいない。ただ静かな夜風が吹いているだけだ。
「なんだよ……誰もいないじゃないか」
「笑い声、ここじゃないんじゃないか」
ヒロキが小さく息を吐いた。皆、口々に安堵した声を出している。
そのとき、背後でバタンと音がした。
俺たちが振り返ると、屋上への扉が勝手に閉まっていた。
「おい! 誰だよ、閉めたの!」
タケシが叫ぶが、返事はない。俺たちは扉に駆け寄り、ドアノブを回したが、びくともしない。
「あれ……鍵がかかってる?」
俺は焦りを感じ始めていた。スマホのライトがちらつき始めたと思うと、次々と画面が真っ暗になっていく。
「電池が切れた!?」
「嘘だろ。まだ電池50%はあったぜ?」
ヒロキが狼狽して声を上げる。
その瞬間、またあの陽気な笑い声が響いた。
「ハハハッ!」
俺たちは硬直したまま、声の方を見つめた。
しかし、そこには何もいない。ただ声だけが屋上中に響き渡っている。
「お、おい……なんだよ、これ。やばいぞ」
タケシの声は完全に怯えている。
その時、屋上の隅で小さく動く影があった。
よく見ると、誰かが背を向けて立っている。
「誰だ!?」
俺が勇気を振り絞って叫ぶと、その人物はゆっくり振り向いた。
それは、見覚えのない中年の男だった。作業服のような格好をしている。異様なほど陽気な笑顔を浮かべているが、その目は真っ暗で何も映していないように見えた。
「いやあ、にぎやかな連中だなぁ!」
男はまた笑った。だが、その笑い声は明らかに異常だ。楽しそうに笑っているのに、なぜか背筋が凍るほど寒々しい。
「あなた、誰なんですか?」
俺は震えながら問いかけた。
「俺か? 俺はただの用務員さ」
用務員? そんな人はこの学校にいた記憶がない。
「この学校に用務員なんて、いませんよ……」
ヒロキが呟くと、男はにやりと口の端を吊り上げた。
「おお、そうだったな。俺はずっと、ずっと昔にクビになったんだ。もしかしたら君らが生まれる前かもしれないな」
男の声は妙に浮いていて、まるで別の世界から聞こえるようだった。
「それからずっと、ここにいる。生徒たちが楽しそうにしてるのを見てるのが好きでなあ。こうして笑っていたら、誰かここにくるじゃないかって思ってな」
「おじさん、もしかして、幽霊……とか?」
タケシの震える声に、男は再び大きく笑った。
「ハハッ!」
その瞬間、男はゆっくり俺たちの方へ歩き始めた。
「仲間になってくれよ。そしたら、もう寂しくない」
俺たちは震えながら後ずさったが、もう逃げ場はなかった。
その時、屋上の扉が突然、勢いよく開いた。
そこには顧問の先生が立っていた。
「お前たち、屋上で何をしているんだ! 鍵がかかっていたはずだが、誰が開けた!」
先生の怒鳴り声に、俺たちは大慌てで屋上を飛び出した。出る瞬間にちょっとだけ振り返ったが、そこにはもう誰もいなかった。
翌日から、あの陽気な笑い声を聞くことはなくなった。
しかし時々、夜の学校の屋上を見ると、あの出来事をふと思い出す。
そして、俺たちはもう二度と屋上には近づかなくなった。

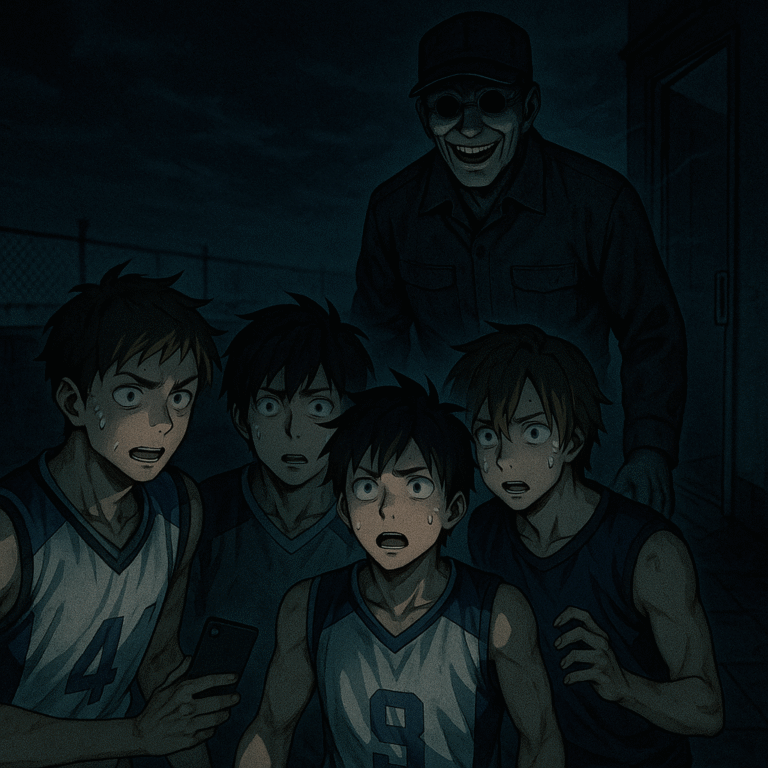


コメント