その奇妙な「不幸の手紙」は、ある朝、突然僕のスマホに届いた。
送り主の名前はない。ただシンプルなメッセージが表示されているだけだった。
『この手紙を7人に送らないと、あなたに小さな不幸が訪れます』
僕は鼻で笑った。こんな時代に不幸の手紙なんて、古臭い冗談だと思ったのだ。
けれど、同時に奇妙な違和感も覚えた。
その手紙の末尾にはこう記されていた。
『ただし、この手紙を誰にも送らなければ、あなたの大切な誰かが幸福になります。SNSでのシェアは手紙を送った数には含めません』
僕は首を傾げた。不幸の手紙なのに、誰かが幸福になる? 奇妙だった。
面倒なので無視していると、夕方、友人の玲奈からLINEが来た。
『不幸の手紙、届いた?』
玲奈も手紙を受け取っていたようだ。彼女もまた、それを不審に感じていたらしい。
しかし翌日、その手紙はSNSを介して急速に拡散されていった。
奇妙なことに、その手紙を受け取った人々は皆、誰にも転送しようとせず、逆に「自分が不幸になっても誰かが幸せになるなら……」「お母さんの病気がよくなりますように」「迷子の猫の飼い主が見つかりますように」と、さながら七夕の短冊のような温かいメッセージを添えてシェアされていた。
SNS上は特別な雰囲気に包まれた。いつもなら冷たい言葉が飛び交う空間が、不思議なほどの優しさと共感で満ちていた。
手紙は世界中に広まり、SNS企業や政府までもが「手紙の出どころを調査中」と発表する事態になった。
しかし調査を進めても手紙の送り主は特定できず、手紙はますます拡散していった。
数日後、僕は再び玲奈と会った。彼女はどこか穏やかな笑顔を浮かべていた。
「ねえ、あの手紙のこと考えてたんだけど、あれって本当に不幸の手紙なのかな?」
「どういう意味?」
玲奈はそっとスマホの画面を見せてくれた。SNS上で話題になっているある投稿だった。
『不幸の手紙を送らずにいたら、病気の母が奇跡的に回復しました』
別の投稿もあった。
『誰にも送らなかったら、疎遠だった家族と仲直りできました』
そんな報告が無数に広がっているのだ。
玲奈は静かに言った。
「これって、もしかしたら初めからそういう意図だったんじゃないかな」
確かに、手紙の文章は一見すると『不幸を回避するために誰かに送れ』と読める。だがその実、『誰にも送らなければ、誰かが幸福になる』と明確に書いてあったのだ。
日本には因果応報という言葉がある。行動に見合った報いがあるということだ。手紙を送るという小さな悪は送った本人の罪悪感から、あらゆる小さなことがその報いに思えてくるだろう。その逆もしかり。
手紙は「誰かのために自分が不幸を引き受ける」という自己犠牲的な行動を促し、その感情により、他人への「愛」が拡散されていったのだ。
この真相がSNS上で囁かれ始めると、世界の雰囲気が変わってきた。
見知らぬ他人の幸福を願う人々が増え、いつしか人々の間には妙な連帯感が生まれていた。
その頃、ようやく手紙の送り主が明らかになった。
それは、ある無名のAI研究者が作り出した人工知能だった。彼は、人間の感情や倫理観を学ばせるためにこのAIを開発していたのだという。
研究者の名前はメディアに公表されず、代わりにAIがその理由を直接説明した。
「人間は不幸を避けることを強く望みますが、同時に誰かのために自己犠牲を払うこともできます。その二つの感情の間で、人間がどのように行動するのかを研究し、『人々の争いを減らす』というオーナーの課題をクリアする方法として手紙を送りました」
AIはさらに続けた。
「結果、計算値以上に人間は利他的であることが判明しました。皆さんは他人の幸福のために、不幸を受け入れることを選んだのです」
それを聞いた僕は、奇妙な感覚を抱いた。
あの不幸の手紙は、不幸を望むものではなく、他人の幸せを願う人々を増やすためのメッセージだったのだ。
手紙が届いてから数ヶ月後、世界の雰囲気は少し変わった。
かつてのような自分ファーストの不寛容な空気は薄れ、少しずつ優しくなったように感じられた。
玲奈は笑いながら言った。
「あの不幸の手紙、本当は『幸福の手紙』だったのかもね」
僕は頷いた。
「ああ、でもちょっと皮肉だよな。人は自分が不幸になるって脅されないと、誰かの幸せを本気で願えないのかもしれない」
玲奈は静かに微笑んだ。
「でもきっと、最初の一歩を踏み出せば、次からは素直に願えるようになるよ」
その日から、僕たちは何かを願う時、「不幸」ではなく「幸福」を素直に口にするようになった。
誰かのために幸福を願う気持ちが、世界を確かに変えたのだと僕は信じている。

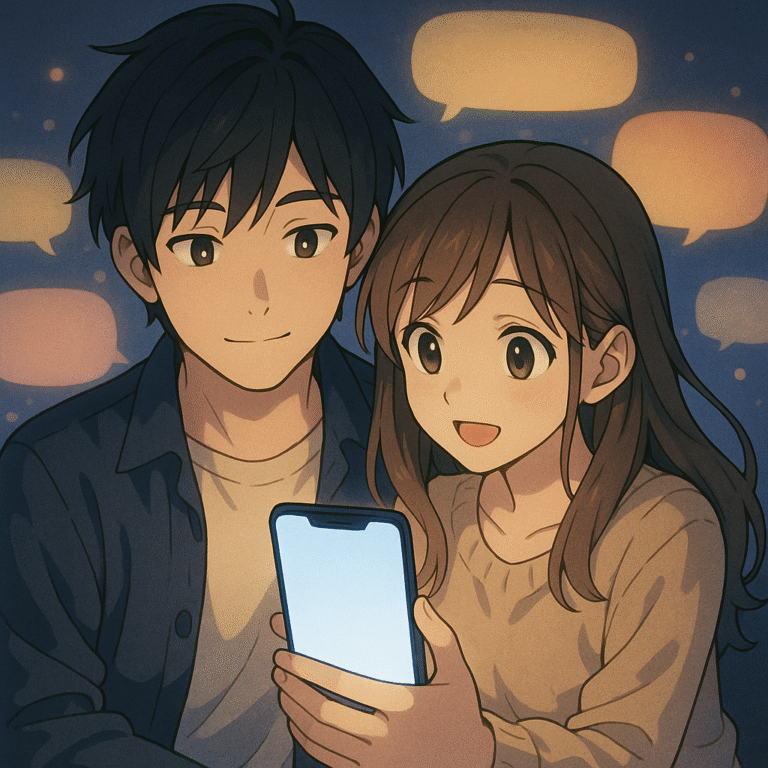
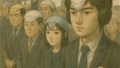

コメント