それは、いつから現れるようになったのかはっきりしない。
午前二時を過ぎたころ、住宅街の細い路地を「何か」がゆっくり歩いていくという噂。
誰もが口をつぐむその存在を、僕は“片目の巨人”と呼んでいる。
身長は三メートルを優に超え、背中をかがめても街灯に頭がぶつかるほど。
異様に長い腕と、濁った白目の中央にぽつんと浮かぶ巨大な黒い瞳がひとつだけ——顔の真ん中に開いている。
巨人は何もしゃべらない。声も出さない。ただ、無音で路地を歩いていく。
いつも決まって午前二時頃、路地の東側から現れ、西の広場に向かって、ひたすら真っ直ぐ歩いていく。
僕がそれを最初に見たのは、三か月前だった。
眠れない夜。窓の外にふと影が通るのを見た。僕の部屋は二階なので、最初は鳥の影かと思った。しかし、外をのぞいて驚いた。翌朝、あれは夢だったのだろうと思っていたが、次の夜も、その次の夜も、やつは同じ時間に同じように歩いていた。
近所の誰かに話してみたが、返ってくるのは一様に曖昧な表情。
「ああ……それね、気にしないほうがいいよ」
「そんな時間まで起きてちゃダメだ」
まるでその存在が常識であるかのように扱い、しかし誰もが曖昧に「それ」の話を避けていた。
だが、三メートルの片目の巨人が日常に溶け込むはずがない。
ある日、意を決して写真を撮ろうとした。しかし、確認した写真は暗い夜の町だけで、巨人は写っていなかった。何度試してもだめだった。
奇妙だったのは、巨人が絶対に誰とも接触しないことだ。
たまに人とすれ違うことがあっても、その人はまったく反応しない。まるで見えていないかのように歩き続けている。路地からは見えないのかもしれない。
ある夜、僕は思い切って巨人に声をかけた。窓の前を通るタイミングで顔を出す。
「……誰なんだ、君は?」
返事はなかった。
だが、巨人は立ち止まり、こちらに顔を向けた。
巨大な単眼がゆっくりと僕を見据える。
喉の奥が凍りつくような感覚。心臓が鼓膜のすぐ近くで跳ねた。
その目に映っているのは僕なのか、僕ではない何かなのか。
一歩、また一歩、巨人が近づいてくる。
だが不思議なことに、恐怖とは少し違う感情が湧いた。
「何かを探してるのか?」
巨人はまたしばらく黙っていたが、やがて足を止め、右手をゆっくりと上げて空を指差した。
空には星がなかった。月もなかった。ただ、漆黒の天蓋が静かに広がっている。
「空……?」
僕が問い返すと、巨人は小さく頷いたように見えた。
そして、そのまま歩き出した。その日も西の広場へ向かって。
次の日、僕は市役所で都市開発の資料を調べた。
広場の場所は、昔は観測所だったという記録があった。天文台が建っていたらしいが、戦後に取り壊されたという。
なんとなく繋がった気がした。
それから僕は毎晩、巨人の後をつけるようになった。
広場に着くと、巨人は中央に立ち尽くし、黙って空を見上げる。
何時間も、微動だにせずに。その場所はまさに天文台があった場所だ。
彼が見ているのは“何か”なのか、それとも“何もない”のか。
ある日、僕は思い切ってその隣に立って、空を見上げてみた。
だが、僕の目には何も映らなかった。
「君には何が見えてるんだ?」
心の中で問いかけると、彼の目がわずかにこちらを向いた。
その瞳の奥に、小さな星がひとつだけ輝いていた。
それを見た瞬間、僕の意識は真っ白になった。
気づけば、自分の部屋のベッドで目を覚ましていた。
朝だった。夢だったのかと思ったが、服には土がついていた。
それからというもの、僕の目には、ときどき人に見えないものが見えるようになった。
人の背中に浮かぶ傷跡、影に潜む言葉、空の狭間に漂う記憶の粒。
誰にも言えないことだったが、不思議と怖くはなかった。
僕はなんとなく気づいた。
あの片目の巨人は、かつて星を見上げていた者、取り壊された天文台の望遠鏡だ。
星が消えたこの街で、ただ一人、星を探し続けている。
そしてたぶん、僕も一緒に星を探している。
今夜もまた、午前二時になれば、片目の巨人は歩き出す。
誰も気づかない道を通って、何もない空を見上げる。



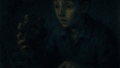
コメント