夏休みの終わり、私たち小学生四人は、友達の家に集まってお泊まり会をしていた。
部屋の床に敷かれたふかふかのクッション、コンビニで買ったお菓子、ポテトチップスの袋、ジュースのペットボトルが散らばる。夏休みだからこそ許される贅沢。
いつもなら恋バナとか将来の夢とか話すはずの時間なのに、その夜はなぜか「怪談しようよ」という流れになった。
外はしんと静まり返って、カーテンの隙間からは夜の闇しか見えない。私は、なぜだか心がざわついていた。
「まずはあいりが話してよ」とさやかが言う。
あいりはうんと小さくうなずいて、目を少し細めた。
「あのね、うちの学校の音楽室、夜になるとピアノの音が聞こえるって有名じゃん。でも、実は私、一回だけ、夕方遅くまで残ってたときに、本当にピアノが鳴るのを聞いたことがあるんだ」
全員が息をのむ。
「しかも、教室に入ったら、知らない女の子がひとりでピアノを弾いてたの。その子、制服も違うし、髪も長かった。こっちに気づかずにずっと弾き続けてて、私、怖くなって逃げちゃった」
空気が少し冷たくなった気がした。
「じゃあ、次はみくね」と、あいりがみくにバトンを渡す。
「わたしは理科準備室の話。あそこ、理科の先生しか入っちゃいけないけど、ある日、放課後に忘れ物を取りに行ったら、中からカチャカチャって音が聞こえてきたの。絶対誰もいないはずなのに、引き出しの開け閉めの音。覗いても誰もいないし、電気も消えてるし。逃げて職員室に行ったら、先生が『あそこ、昔変な事故があってね』って……」
みくの声が少し震えていた。みんな、静かに息をのみながら、じっとみくを見つめていた。
「最後、さやかの番だよ」と、みくが言った。
さやかは少し考えるふりをして、ぽつりと語り始めた。
「体育館の話。私、バスケ部だから、よく夕方遅くまで残って練習してたんだけど、ある日一人でフリースローの練習してたら、誰もいないはずの体育館で、後ろからずっとボールの音が聞こえてたの。振り向いても誰もいない。でも、確かにポンポンって、ボールの弾む音だけはずっとしてる。帰り道、鍵を閉めてからも音が聞こえて、すごく怖かった」
話が終わると、私たちはしばらく黙り込んでいた。外の虫の音だけがやけに大きく聞こえる。
「……ねえ、最後は私だよね?」
私がそう言うと、その場の全員が驚いたようにこちらを見た。
「私の番だよね」
でも、不思議と誰も何も言わない。
「私……」
三人の視線は私に集まったままだ。あいりが、少し低い声で聞いた。
「ねえ、あなた誰?」
みくも、じっと私の目を見つめてくる。
「ねえ、ほんとに誰?」
さやかも、いつのまにか声をひそめて、
「い、今急に来た……よね? あなたの名前、知らないんだけど?」
私は言葉が出なかった。ずっとここにいたのに。
「え……私……?」
記憶をたぐろうとするけど、何も浮かんでこない。自分の声さえ、どこか遠くから聞こえるようで、手も足も重い。頭もぼんやりする。
「私……って、誰だっけ……?」
三人は、私から一歩ずつ離れていく。部屋の隅っこまで、まるで見えない壁でもあるみたいに、寄り添って震えていた。
私は、その場にぽつんと残されていた。
窓の外で、どこか遠くでピアノの音が微かに鳴ったような気がした。
そうだった。
私は学校にいて、楽しそうだったから憑いてきちゃったんだった。忘れてた。私は自分の存在がすうっと薄れていくのを感じていた。
帰ろう。
窓からするりと外に出ると、背後から「キャー!」という悲鳴が聞こえてきた。
もうそろそろ、私が「私」である必要はないのかもしれない。
誰かの怪談の中の、「知らない誰か」として、この夜に溶けてしまいたい気がした。
──私は自分が誰だったのか、思い出せなくなった。
この話をこうして語っている「私」は、いったい誰なのか。あなたにも、それが分かりますか?

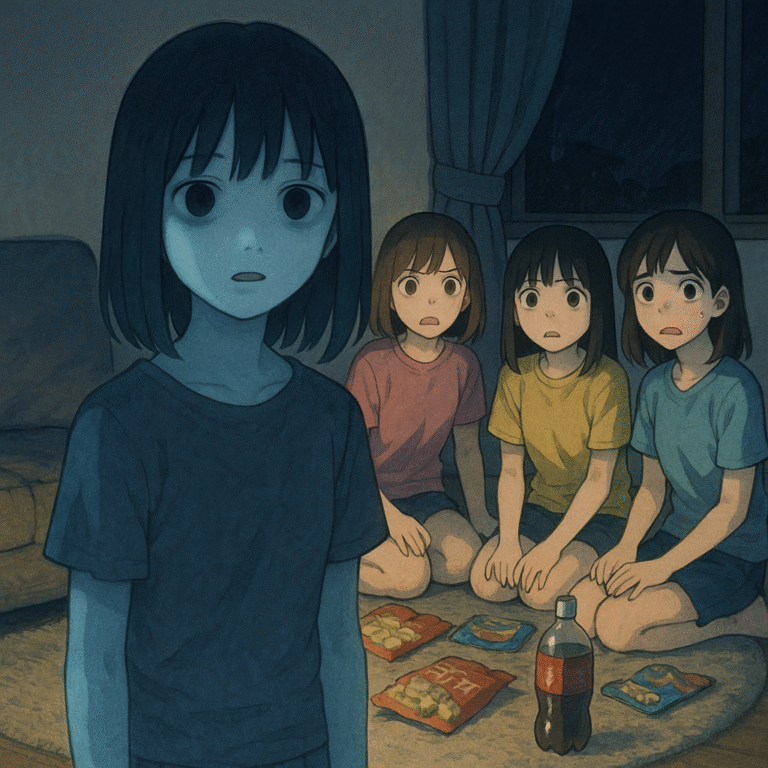


コメント