「え、なんか……全然知らないやつが僕の席のとなりにいるんだけど?」
これが、僕が最初に思ったことだった。
月曜日の朝。
カフェインとエナジードリンクのダブルパンチで無理やり目を開かせて出社した。
いつものように自分のデスクに座ろうとしたとき、違和感が走った。
普段は空席のはずの隣のデスクに、見知らぬ男が座っている。
何食わぬ顔をして、パソコンを使用し、書類を机に並べて作業していた。
「誰?」と思ったのは僕だけじゃないようだ。
周囲の同僚たちも、ちらちらと視線を送り合っている。けれど不思議なことに、誰も声をかけない。あまりにも当たり前という様子でそこにいるので、「誰ですか?」と言いにくい雰囲気になっていた。
妙な沈黙の中、その雰囲気にのまれた僕は「おはようございます」と口にしてしまった。周りの空気が動いた。「自分が知らないだけでやっぱり社内の人なんだ」という安堵した空気が流れる。流されやすいのは僕の悪いところだ。
男はにこりと笑い「おはようございます。今日も暑いですね」と自然に返した。まるで、ずっとここにいたかのような態度で。
……あれ。やっぱり前からいた人?
午前中は仕事に追われ、彼の存在を考える暇もなかった。
だが、昼休み。
社員食堂で隣の席に座ったのは、またしても彼だった。
「そういえば、先週のプレゼン、すごくよかったですよね」
「……先週?」
先週のプレゼンに関して、彼が知っているはずはない。だって今日の朝、突然隣の席に現れた人じゃないか。
出社していたなら覚えているはずだが、先週も先々週も、隣のデスクは空席だった。
「あの、あなたって……」と問いかけようとした瞬間、向かいに座っていた先輩が割り込んだ。
「いやー、定食はやっぱり唐揚げに限るよな!」
気づけば、先輩も彼も自然に食事に混ざっていた。誰も不思議がらない。彼がそこにいるのが当たり前のようになっている。やっぱりおかしいのは僕の方なのか。
午後の会議室でのことだ。
彼は当然のように僕のプロジェクトチームに加わっていた。メンバーの一人として発言し、メモを取り、議論を進めている。
誰も違和感を口にしない。会議の終盤、彼はこう言った。
「僕らはもっと一体感を持つ必要があると思うんだ。このプロジェクトは絶対に成功させたい。スラックの返信が遅い人がいると、どうしても仕事が滞ってしまう。仕方がない場面もあるかもしれないけど、お互い気をつけようよ」
それは長い期間ともにプロジェクトを進めてきたメンバーならではの発言だった。確かに「あの人の返信待ち」、「この人の連絡待ち」みたいな無駄な時間がこのチームには多い。チームメンバーだからこそわかる問題点だった。
定時を過ぎ、僕は意図的に残業を引き延ばした。隣が気になって仕方がなかった。
彼がいつ帰るのかを見届けたかったのだ。夜も更けてくるとオフィスに残っているのは僕と彼だけになった。
「帰らないんですか?」と声をかけると、彼は穏やかに微笑んだ。
「帰る場所なんて、ないからね」
その答えに、背筋が冷えた。
「……どういう意味ですか」
「ここが僕の席なんだ。ずっと前から」
「ずっと前って……」
僕は勇気を振り絞って口にした。
「昨日まであなたはいなかった……ですよね?」
僕の決死の発言に彼はにこりと笑っただけだった。
次の日、彼はまた隣にいた。
同僚たちも昨日同様にチラチラと見ながらも普通を装っている。いや、むしろ昨日より彼の存在に慣れてきているような雰囲気すらある。
「ねえ、昨日さ……あの、隣の人、急にいたよな」と小声で後輩に訊ねた。
後輩は怪訝そうに僕を見た。
「何言ってるんですか。あの人、前からいましたよ」
言葉が出なかった。記憶が書き換えられているのか。それとも、僕がおかしいのか。夕方、隣の彼が小さく囁いた。
「大丈夫ですよ。すぐに慣れますから。周りの方もみんなそうでしょう?」
確かに。今朝はチラチラと彼を見ている人がいたが、午後になるとほとんどそういった様子を見せる同僚はいなくなっていた。
その夜、帰りの電車の窓に映る自分の顔を見ながら思った。明日も彼は隣にいるだろう。
そして、いずれ僕も――彼を疑問に思わなくなるのか?
彼はすっかり「いつものメンバー」になっていた。
だが、おかしいのはそれだけじゃなかった。翌週には、さらにもう一人、見知らぬ女が増えていた。
僕のチームには女性は三人しかいないはずだ。だが四人いる。彼女は自然に会議に参加し、笑顔で意見を述べる。
「市場調査のデータですが――」
初めて見る顔なのに、皆は頷きながらメモを取っていた。誰も不審に思っている様子はない。
「誰?」と聞きたかったが、聞けなかった。いったいこの会社で何が起こっているんだろうか。
木曜日。
隣の島にも「新しい人」が座っていた。茶髪の青年。彼は気さくに雑談を振りまき、休憩室では同僚たちと笑い合っていた。僕だけが彼が誰なのか知らないようだった。
金曜日の夕方。
オフィスを見渡すと、見知らぬ顔が四、五人は混ざっていた。だが不思議なことに、誰も違和感を覚えていないようだった。
「君もすぐ慣れるよ。人が増えるのは自然なことなんだ」
隣の彼がほほえみかけてくる。僕は返事ができなかった。
週が明けて月曜日。
出社して唖然とした。オフィスの三分の一が、知らない人で埋まっていた。スーツ姿もあれば、ラフな服装の者もいる。その誰もが当たり前のようにパソコンを操作し、書類を片付け、電話に応対している。
一方で、以前からの同僚はなぜか少なくなっていた。席が空いたわけではない。ただ、知らない人に入れ替わっていた。
そして翌日、さらに入れ替わった人が増えた。
今度は課長の隣に、見知らぬ初老の男が座っていた。
課長は笑顔で談笑している。「長い付き合いだからな」と言っていたが、そんなはずはない。
さらにその翌日。もう半分以上が「知らない人」になっていた。
会議室で発言するのは彼らばかり。気づけば議事録を取っているのも彼ら。僕の知るオフィスは、どんどん塗り替えられていった。
「君もそろそろだね」
隣の彼が笑顔で話しかけてくる。
「……どういう意味だ」
声が震えていた。
男は柔らかく笑いながら言った。
「そんなに心配しなくても大丈夫。君らは消えない。ただ、役割が変わるだけ」
意味は理解できなかった。
だが次の瞬間、視界の端に映った自分のデスクで、知らない誰かが書類片手にパソコンを操作していた。同僚たちは、ごく自然にその人物に仕事の話をしている。
「この議事録に載ってる市場調査の件だけど――」
「ああ、それか。プロジェクトの遅延が心配だな。明日A社で――」
それは本来僕が聞くべき話だ。
「大丈夫。すぐに慣れる」
隣の男が囁いた。その声はやけに心地よく響いた。気づけば、僕はただ笑って頷いていた。
――オフィスには、また一人、新しい顔が増えていた。

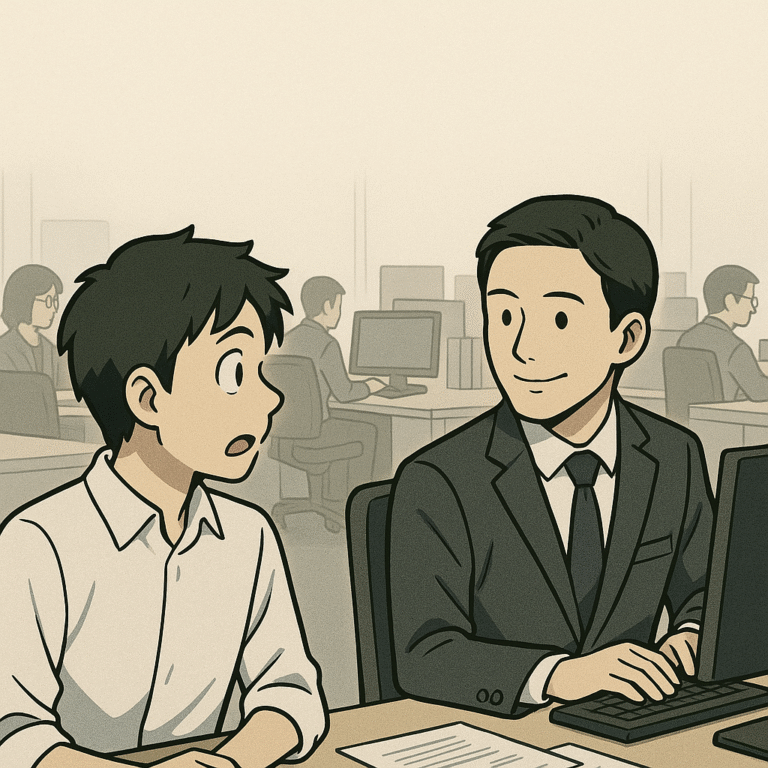


コメント