いや聞いてくれ、本当におかしくなったんだと思うんだ。
俺は昔からアニメ好きだったんだけど、ここ数年は擬人化作品ばかり追いかけてたんだ。戦艦や競走馬が美少女になったり、武器がイケメンになったり、地名がキャラになったりするだろ? そういうのを追いかけすぎて、脳が完全に「なんでもキャラ化していい」っていうフィルターをかけちゃったんだよ。もっというと、俺の中の何かがぶっ壊れちまったんだ。そうでなけりゃ説明がつかないんだって。
最初に現れたのは、G……ゴキブリだった。いや、正確には「ゴキブリのはずの存在」だ。
暗い台所の隅でカサカサ音がしたから、絶対にヤツだと思ったんだよ。スリッパを握って身構えた瞬間、シンクの下からひょいと出てきたのは――黒髪ロングで制服姿の美少女だった。ぴょいんと長いアホ毛がはねる。
「こんばんは、お兄ちゃん」
俺は硬直した。スリッパを振り上げたまま、心臓が止まるかと思った。
そいつは確かにゴキブリの動きをしていた。床をすばしっこく駆け抜け、壁をクライミングするみたいに垂直に登る。
それなのに、見える姿は美少女。短いスカートがひらひら、長い髪とアホ毛がぴょんぴょんと揺れている。控えめにいって――めちゃくちゃかわいい。
「な、なんで……」と声が漏れた。
彼女はくるりと振り返り、にこっと笑った。
「わたし、じぃこ。よろしくね」
じぃこ……G子? 完全に頭がおかしくなったと思った。
でも、それは始まりにすぎなかった。
翌日、ベランダに出るとアリの行列がいた。よく見ると全員、赤い袴姿の小さな巫女少女。無言で何かを運びながら、整然と歩いていく。リーダーっぽい子が振り返り、俺に一礼してきた。
「働きますので、通していただけますか」
足が震えた。
その夜、蛍光灯に蛾が飛んできた。
ひらひら舞うそれは、純白のドレスをまとったお姉さん。光に吸い寄せられながら、不思議な歌を歌っていた。
蝶は妖艶な舞踏会の姫。蜂はツンデレの槍使い。
ダンゴムシがくるんと丸まると、ランドセルを背負った幼女が「もうやだー!」と地面で転がっていた。
俺の世界は一晩で変わったんだ。
街に出ると、ありとあらゆる虫が美少女の姿をしていた。
カナブンの金髪ツインテールが信号機の下で大騒ぎしていて、セミの短髪少女たちが「地上では時間がないぞー」「いっそげー」と木にしがみついて大騒ぎしている。
笑っちまうだろ? でも、俺は笑えなかった。
だって、彼女たちはただ「美少女に見える」んじゃない。本当にそこにいて、話しかけてきて、俺の生活に干渉してきたんだ。しかも全員めちゃくちゃにかわいい。
はたから見ればかなり気合の入った変人に見えるだろう。虫を見て、ニヤニヤしているなんて、絶対にヤバい。でもニヤニヤはとまらないんだよ。オタクならわかるだろ?
ある晩、また台所にじぃこが現れた。
「ねえ、ねぇ。お兄ちゃん、この間は殺さないでくれてありがとう」
彼女は真っ直ぐな目で俺を見た。きゅるんとした真っ黒な目がかわいらしい。
「お腹すいちゃった。なんか食べ物ない?」
じぃこは微笑んだ。わがまま系妹キャラ!!
「あるよ。ポテトチップスをあげようか」
「やたー! ポテチ大好き! お兄ちゃんも大好き!」
――これは祝福じゃない。呪いだ。
俺は世界中の虫を、美少女の姿で見ることになった。誰も信じてくれないし、誰も共有できない。
どこかの飲食店でじぃこの仲間たちがいても、店員はためらいなく殺してしまうのだろうし、俺はそれを目撃してしまうかもしれない。
公園で蟻たちが無言で行列していても、子どもたちは砂遊びをしている。下手をしたら、わざと踏んで遊ぶ子もいるかもしれない。
俺だけが、その「もうひとつの世界」を背負わされている。
じぃこたちは少しずつ数を増やしている。俺の部屋にも、台所にも、そして外の世界……駅のホームや、地下街にもいる。
そして、じぃことはまたキャラが違っていて――全員かわいい。
「お兄ちゃん、お腹すいちゃったよ」
じぃこがそう言った。
俺は寝返りも打てず、ただ天井を見つめていた。
俺の世界はもう、虫……美少女たちに囲まれている。
そして俺は、笑いながら思ったんだ。
「じぃこ、やっぱりめっちゃかわいいな」
……頭がおかしくなったのか、それともこれが真実なのか。どちらにせよ、もう後戻りはできないのは確かだ。

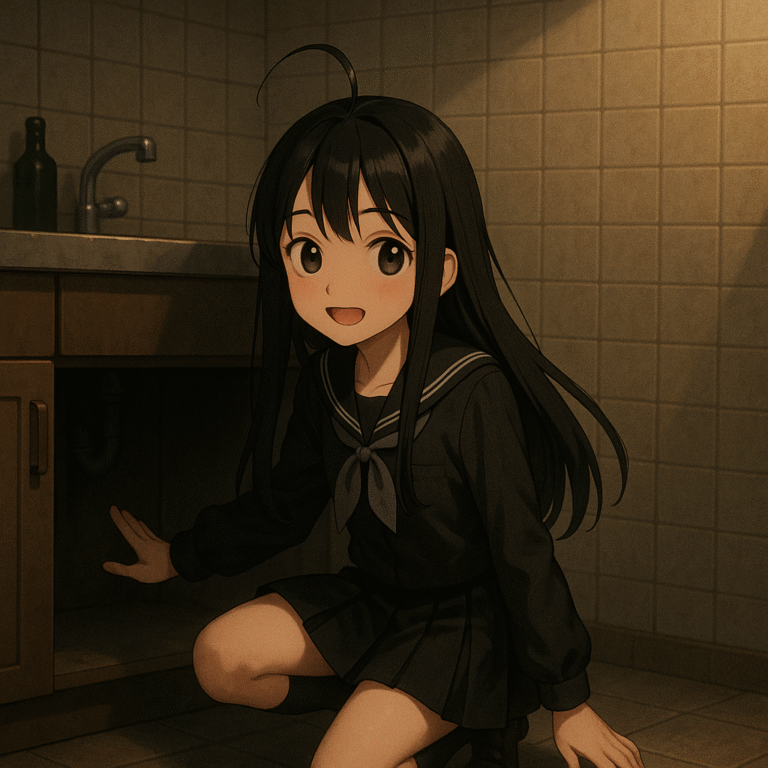


コメント