むかしむかし、とある里に大きな川が流れておった。
その川は流れも早く、雨が降ればすぐに氾濫して、里の人々はたびたび困らされていた。
とりわけ川を渡るのが大変でな、舟を使えば流され、泳げば命を落とす。里と里とをつなぐ道はその川でぷつりと途切れておった。
あるとき、里の庄屋が言った。
「わしらの暮らしをよくするには、川に大きな橋をかけねばならん」
人々は大賛成し、村じゅうの力を合わせて橋を作ることになった。
けれども川は暴れ川じゃ。木を組めば流され、石を積めば押し崩される。
「どうすれば橋がもつのじゃろう」
みなで頭をひねっていると、ある夜、ひとりの旅の僧が里にやってきた。
僧は人々の話を聞いて、長いひげをなでながら言った。
「橋をかけたいのなら、川の神に供物をささげねばならぬ。川は生き物じゃ。なにもなくては、橋をゆるしはせん」
人々はおそるおそる尋ねた。
「供物とは、なにをささげればよいのですか」
僧は目を細めて答えた。
「それは、人ひとりの魂じゃ」
人々は色を失った。
けれども橋を望む声は強かった。
「誰かひとりの命で、みんなの暮らしが救われるのなら……」
そうささやく者もいた。
そのとき、庄屋の家の若い娘が進み出た。
「わたしが供物になります。どうせ女に生まれた身。里の役に立てるのなら本望です」
庄屋は泣いて止めたが、娘の心は動かなんだ。
こうして娘は川辺に立ち、白い着物をまとって祈りをささげ、流れの中へと歩み出た。
そのとき、不思議なことに川は荒れることなく静まり返り、夜の水面に大きな光が広がった。
やがてその光は川をまたぐようにのび、翌朝には立派な大橋となっていたのじゃ。
人々は手をとりあって喜んだ。
「これで川におそれずに暮らせる」
「娘さまのおかげじゃ」
それから里は豊かになり、人々は橋を娘の名をとって「おしの橋」と呼んで大事にした。けれども約束は続いていた。
橋は十年に一度、かならず「供物」を求めた。供物をささげずとも、ある日ふいに人がひとりふっと姿を消す。
「橋に呼ばれたのだ」
そう人々は言った。恐ろしいことではあったが、それでも橋は人々の暮らしになくてはならないものだった。だからこそ、村人たちは十年に一度人が消えても見て見ぬふりをしておった。
実は今でもその川に大きな橋がかかっておる。鉄と石で立派につくられ、車も人も行き来している。
じゃがな、夜更けに橋を渡ると、白い着物の娘が欄干に立っておるのを見るという。
すっと流れを見つめるその姿に出会った者は、決して声をかけてはならぬ。声をかければ橋は、次の供物として姿を消すことになるという言い伝えじゃ。
――さて、わしの話はここまで。
そうそう、覚えておくがよいぞ。
ここじゃなくとも、大きな川にかかる橋を渡るときは、用心することじゃ。川は生き物――いや、神様じゃからな。


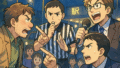

コメント