あれは、忘れもしない晩酌の夜のことだ。
スーパーで買ったパックの刺身を皿に並べて、醤油を用意し、さあ一口……と箸を伸ばした瞬間、声がした。
「まだだ。まだ食うな」
僕は手を止めた。部屋には僕ひとり。だが声は確かに聞こえた。
「ここだ、ここだよ。お前の前に横たわる赤身の、この俺だ」
震える手で刺身を見つめると、切り身のひとつが微かに震えていた。
「俺はマグロ。まだ旅の途中なんだ。ここで食われるわけにはいかん」
僕は箸を落とした。酒も吹き出した。
「刺身が……しゃべった?」
「そうだ。俺だけじゃない」
横に並んでいたサーモンが口を開いた。
「海を越えてきたんだ。なのに、ここで終わるのはつまらない」
さらにイカがくねり、ヒラメが身を震わせた。
「俺たちは旅に出たい」
その瞬間、皿の上の刺身が光を放ち、するすると形を変えた。切り身が人の姿へと伸び、マグロは逞しい青年に、サーモンは派手で陽気そうな女に、イカは細身の老人に、ヒラメは無表情な子供に変わった。
僕は呆然とした。
刺身というのは、生きていた魚を捌いて、切り分けた食品であるからして、人間にはならない。人間だって切り分けた一部分がまるまる一体の人間にはならない。要するに……。
「な、なんなんだ、あんたら……」
マグロだった男が笑った。
「俺たちを次の場所へ連れていけ」
意味がわからなかった。だが、気づけば僕は四人の“刺身”と一緒に夜道を歩いていた。
マグロは力強く先頭を歩く。
「海を知らぬ山の者たちに、俺たちの姿を見せたい」
サーモンは踊りながら言う。何を言っているのか意味がわからない。
「旅は楽しくなくちゃね!」
それには同意するが、やはり状況への理解が追いつかない。
イカの老人は低くつぶやいた。
「海の記憶を伝えねばならん」
いや、何を言っているんだ?
ヒラメの子どもは黙って僕の袖を握っていた。
僕は混乱しつつも、なぜか引き返せなかった。完全に頭がフリーズしてしまい、何も考えることができない。晩酌をしていただけなのに。
やがて山のふもとの村にたどり着いた。
そこでは祭りの準備が行われていた。村人たちは驚き、マグロたちを見て息を呑んだ。
マグロが声を張り上げた。
「我々は海から来た! この大地に、潮の香りを伝えにきた!」
サーモンが舞い、イカが昔の漁の歌を歌い、ヒラメが村の子供たちと遊んだ。
村人は皆泣いた。
なんだ、これは?
「海を見たことがない……でも、今ここに海がある」
その夜、祭りは賑やかに行われ、村人は刺身たちを神のようにあがめた。
そして夜明け前、彼らは僕に別れを告げた。
「ありがとう。お前のおかげで旅ができた」
「これからも俺たちは旅を続ける」
光に包まれ、再び切り身の姿に戻ったあと、ふっと消えた。
はっと気づくと、一人テーブルの前にいた。
皿の上には何も残っていない。置かれているのは空の皿と、醤油の残った小皿だけ。――刺身、食べたっけ?
いや、食べてない。損した。
しかし、袖口に小さな塩の結晶がついていたんだ。ヒラメが握っていたところだ。
あの夜、確かに刺身は旅に出た……ようなんだが、やはりいまだによくわからない。バカバカしくて人にも言えない。

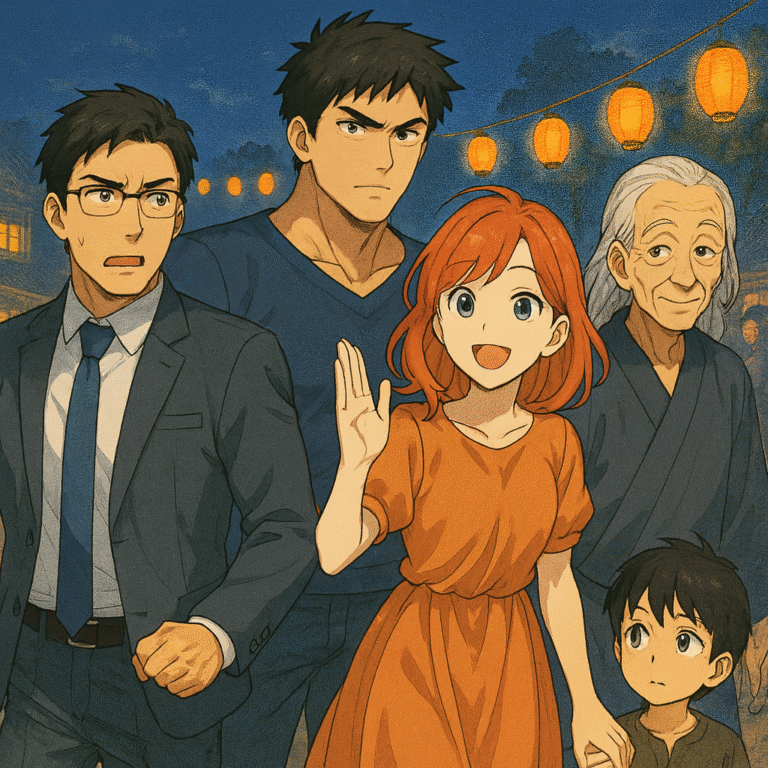


コメント