俺の名前はリアン。
ここでは、俺のような人間を「狩人」と呼ぶ。ただし獣ではなく、森の化物を狩るための狩人だ。
この村では、人が生まれると同じ日に犬が一匹生まれる。生まれた人と犬は対(つい)と呼ばれ、どちらかが死ねば、もう一方も同時に死ぬ。だから誰もが、自分の犬と共に育ち、働き、老いていく。俺にとっては、それが当たり前だった。
俺の相棒はリト。毛並みは黒に近い灰色で、瞳だけがやけに青い。子犬の頃から俺より賢かった。俺が言葉を覚えるより早く、リトは「座れ」も「伏せ」も早くから理解していた。気づけば俺の半分は、リトでできていた。
十歳になると、村の子どもはみんな森の学校に通う。
人の教官と犬の教官がペアで、戦い方、追跡の方法、王都への報告書の書き方まで叩き込まれる。
「人だけじゃ生きられない。犬だけでも生きられない。お前たちはふたりでひとつだ」
それが口癖の先生の言葉だった。
やがて成人を迎えると、俺たちは「王都猟犬隊」に登録される。王都からの指令が届くたびに、俺たちは森の奥へ入っていく。狩りの対象は獣ではなく、「影持ち」と呼ばれる存在――心が壊れ、森に棲みつき、形を失った怪物たちだ。
ある時、王都から無茶な指令が届いた。
「森の北端に現れた影持ちを討伐せよ。ただし、村を通らずに直接向かえ」
普通なら補給や準備のために中継地を経由するのが常識だ。だが命令は絶対だ。
夜明け前、俺とリトは森に入った。霧が深く、樹々がやけにざわついていた。風が鳴るたび、リトの耳がぴくりと動く。
「行こう、リト」
声を出した瞬間、リトの瞳が一瞬だけ青く光った。俺の中で何かが反応する。村の者たちは対の絆を魂の糸と呼ぶ。心を繋ぐ見えない糸。強く結ばれていればいるほど、互いの感情が流れ込むという。
森を進むうち、空が白んできた。霧の向こうに、黒い影が立っていた。人の形をしている。だが目も口もなく、腕の先が土に溶けている。それが影持ちだ。
リトが低く唸る。俺も剣を抜いた。
「リト、行け!」
「ウォン!」
リトが音もなく駆け出す。影持ちはぬるりと動き、地面に広がった。霧が歪んだ瞬間、俺の足がすくわれる。地面の下に、もう一体いた。
リトが飛びかかり、俺を押しのけた。青い光が弾け、影が裂ける。リトの牙が影持ちの腕に食い込んだ――と思った瞬間、リトが弾き飛ばされた。
「リト!」
駆け寄ると、リトの胸が上下していた。だが目が半分閉じている。俺の中で何かが痛む。魂の糸が軋んでいる。
「立て、リト! 一緒に行くって言っただろ!」
リトが小さく鳴いた。次の瞬間、リトの瞳が強く光る。俺の手にも熱が走る。視界が一瞬白くなり――気づいた時、影持ちは消えていた。
周りの霧も、すっかり晴れていた。
リトは倒れたままだった。俺の腕の中で、小さく尻尾を振る。
「お前……無茶しやがって」
「クゥン」
声が震えた。笑ってるのか泣いてるのか、自分でもわからなかった。
村へ戻ると、王都からの報告要請が届いていた。討伐完了。被害なし。それだけでいい、と上からは言われている。
でも、本当は言いたいことが山ほどある。影持ちは、ただの怪物ではない。あれは、王都が切り捨てた人たちの残滓なんだ。罪人や、被差別者、病で追放された者たちが、森に流れ着き、姿を変えた結果が影持ち。俺たちはその後始末をさせられている。
リトは横で丸くなって寝ている。あれから数年が経ったが、まだ元気だ。俺の髪に白いものが混じり始めても、リトの目はあの頃のままの青をしている。
「なあ、リト。いつまでこうしていられるんだろうな」
リトは返事の代わりに一度だけ尾を振った。
「俺たちも、いつか影持ちになるのかな」
俺たちも王都から差別を受けている人間なんだ。病めばいずれ影持ちになる。ならない者もいるが、王都を憎んでいる者はなりやすい。俺はたぶん影持ちになる。
「そんときは、誰が俺たちを狩るんだろう」
リトは立ち上がって、俺の手に鼻を押しつけた。ああ、そうか。きっと誰も狩らない。ふたりでひとつのまま、森に溶けていくんだ。
夜、火を焚いてリトの毛を梳く。昔は黒かった毛が、月明かりの下で銀色に見えた。
「リト、次に生まれても、お前と一緒がいい」
「クゥン」
そう言うと、リトはゆっくり目を閉じた。焚き火の音だけが響く。そして俺も目を閉じた。
次に目を開けた時――俺の腕の中には、小さな灰色の子犬がいた。その目は、どこまでも透き通る青をしていた。
#499 影を狩る者たち
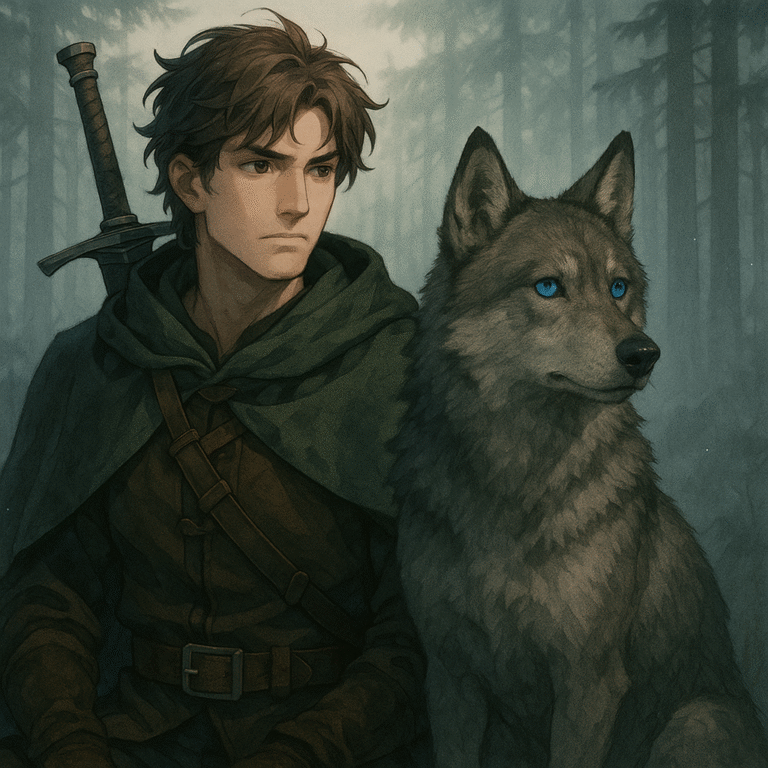 ちいさな物語
ちいさな物語
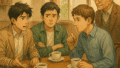

コメント