重いものを引っ張っている夢を、俺は定期的に見ている。
季節に関係なく、年に三、四回ほど。体感では汗だくになっているのに、目が覚めると何ともなっていない。ただ不思議と筋肉痛にはなっている。
夢の中では、俺はいつもロープを握っている。先は見えない。一人で引っ張っていることもあれば、他にも一緒に引っ張っている人がいることもある。その人たちは知り合いではない。みんな黙ってロープを引いている。
足元は砂利道だったり、アスファルトだったり、時には海の上だったりする。風景は毎回違うのに、空の色だけは同じだ。曖昧な灰色。夕方のようで、朝のようで、なぜか夜のようでもある。
重いものを引いている感覚はある。だが、何を引いているのかはわからない。
俺はある日、夢の中で後ろの人に話しかけてみた。その日、一緒に引っ張っているのは、その人だけだった。
「俺たちは何を引いてるんですか」
その人は口をパクパクさせていた。声が出ないらしい。代わりに胸ポケットからメモ帳を取り出して何かを書いた。
『知ってはいけない』
そして次の瞬間、夢が終わった。
目が覚めてもしばらく心臓がバクバクしていた。寝ぼけたまま冷蔵庫の水を飲み、ふと見ると、手のひらにロープの跡のような線が残っていた。もちろんそんなはずはない。でも、指先も少しだけ赤かった。
あれは夢なんだから気のせいに違いない。どうせベッドの角にでもぶつけたんだろう。
それから数日後、再びあの夢を見た。
今度は雪の上を歩いていた。ロープは冷たく凍りついている。後ろにいた人が転んで、列が一瞬止まった。今日はたくさん人がいる。
前にいた男が振り向いて叫んだ。
「立て! 止まるな!」
声が異様に響いた。まるで洞窟の中にいるみたいに。
「これは何を引いてるんですか!」俺は叫んだ。男はこちらを見て、少しだけ笑った。
「未来だよ」
……未来?
「なにそれ!」
「知らないほうがいい」
まただ。いつも知らないほうがいい。でもどうしてだ?
目が覚めた。スマホのアラームが鳴っている。今日の予定欄には「歯医者」と「スーパー」と……「?」のマークがあった。誰が入れたんだ、こんなの。削除しようとしたら、アプリがフリーズした。
このとき「未来を引いている」という夢のことが、なぜか思い出された。
その夜も夢を見た。今回は町中だった。アーケード街の真ん中を、みんなでロープを引っ張っている。買い物客がこちらを見ていた。
「頑張れー!」
「もうちょっとだ!」
何を応援されてるのかわからない。隣の中年男性が言った。
「最近、引き手も見物人も増えたね」
そういえば、最近は一人で引っ張ることがなくなっていた。
「これ、どこへ向かってるんですか?」
「向こうですよ」
男は指をさした。そこには巨大な扉があった。金属のような石のような、奇妙な質感。表面には無数の文字が刻まれていた。その文字は読めなかった。
「あれを開けたらどうなるんですか」
「誰も開けたことない」
「じゃあ、なんで引っ張ってるんですか。開けないと進めないですよね」
「とりあえず引っ張るのが決まりだから」
朝。
起きたら腕がひどい筋肉痛だった。昨日、特に何もしていないのに。俺は笑った。まるで現実と夢がつながってるみたいだ。
そう思った瞬間、玄関のチャイムが鳴った。インターホンを覗くと、スーツ姿の男が立っていた。肩にはロープが掛かっている。
「こんにちは。夢労連(むろうれん)の者です」
「……どこですか、それ」
「夢を引く人々の組合です。あなたはだいぶベテランみたいですね」
「ちょっと待ってください。まだこれ、夢ですか?」
「どっちだと思いますか。それはさておき……」
男は笑顔で分厚いファイルを差し出した。
「あなたが引いているものの契約内容です。ご確認を」
ファイルにはこう書かれていた。
【案件名】地球【進捗】約0.003%【参加者】約80億名【備考】夢経由で作業継続中。実体確認不要。
俺は乾いた声でつぶやいた。
「地球って……これ、全員で引いてるんですか?」
「はい。引き続けてください」
「何のために?」
「知る必要のないことです」
男は深くお辞儀して帰っていった。
それからというもの、俺は毎晩その夢を見るようになった。同じ灰色の空、同じロープ、同じ沈黙。
目が覚めると、必ずロープの感触が指に残っている。
そして今日も夢を見た。
今度は海の上。水平線の向こうに何かが見える。俺は確かに、引いている感覚を感じる。ロープの先、何かが浮かび上がろうとしている。
白い影だ。大きい。もしかして――
そのとき、全員の動きが止まった。頭の中に声が響いた。
「それを知ってはいけない」
全身が痺れ、視界が真っ白になった。
目を開けると、オフィスのデスクに座っていた。うたた寝をしていたようだ。最近、夢の中の肉体労働で体が休まった気がしない。
部長がやってきて笑った。
「おい、寝てたろ?」
「引っ張っていました」
「――だろうな」
隣のデスクでは、同僚たちが静かにロープを握っていた。床を這うようにして、一本の太いロープがオフィスの外へ伸びている。
俺は息を吸って、それを握った。
ここが夢なのか現実なのか、だんだんわからなくなっていた。


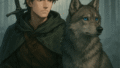

コメント