朝、目覚ましの音で目を覚ました。……はずだった。
枕元でベルが鳴っている。だが、体が動かない。目を開けると、見慣れたはずの天井がどこか違う。
薄暗い部屋。天井には煤けた模様。布団の下の感触は硬い。
ベッドじゃない。古い木の寝台だった。
「……夢?」
声を出すと、部屋の空気がざらりと震えた。誰もいない。
壁掛け時計が答えるようにコチコチと音を立てる。古風な振り子時計だった。見たことがないものだ。ここはまだ夢の中……か?
針は午前6時を指しているが、秒針だけがやたらと早い。そんなに早く時間が進んだら遅刻してしまう。
「目覚ましが鳴ってるのに、起きられない」――これが現実なら相当まずい。やはりまだ夢の中だと気づいた瞬間、背筋が冷たくなった。
部屋のドアを開けると、長い廊下が続いている。
絵画と蝋燭。どこか洋館のような造り。床の木がギシギシ鳴るたび、足音が遅れて響く。まるで自分の後を誰かがつけてくるみたいで気味が悪かった。
最初の部屋は書斎。
机の上に古びた本が開かれている。
《四つの時を止めよ。されば目覚めの門は開かれる》
下には屋敷の見取り図のような絵――そこに四つの時計が描かれていた。壁掛け、置時計、懐中時計、塔の上の大時計。
これを全部止めていくのか。まるでゲームのクエストみたいだ。
でも、これはただの夢じゃない。そう思わせる妙な「現実味」がある。空気の湿り気、埃の匂い、服のざらつき。全部、本物みたいに感じる。
「……四つの時計を止めれば起きられるのか。間に合うのか?」
そう呟いた瞬間、どこかでカーンと低い鐘の音が鳴った。
書斎の時計の絵にしたがって進むと、廊下の突き当たりに最初の時計があった。金の縁取りが施された立派な壁掛け時計。
しかし、触れようとした瞬間、ガシャンと壁から腕のようなものが伸び、俺の手首を掴んだ。
「うわっ!」
冷たく硬い感触。木の枝のような手が、俺の腕を締め上げる。とっさに床に落ちていた燭台を掴み、叩きつけた。木の腕が砕け、時計のガラスにひびが入る。
秒針がピタリと止まった。
すると、どこからともなく微かな風が吹き抜け、囁く声がした。
「一つ、止まった」
こんな物理的に破壊するみたいなことでも止められるんだ。
次の時計は食堂だった。
長いテーブルの中央に、豪華な銀の置時計。なぜそんなところに時計を置くのだろうか。
食堂には誰もいないのに、テーブルの上には皿、カトラリー、スープ、パン、果物が並んでいる。
「……誰の食事だよ」
スープ皿の中に、泡が浮かんで文字を描いた。
《食事を終えぬ者、時を終えられぬ》
仕方なく、スプーンを取る。スープは温かく、香ばしい匂いがする。ひと口すすると――舌がピリッと痛んだ。毒だったりして? 夢の中で死んだりしないよな?
出されているものをすべて食べ終えて一息ついた。すると時計の分針がひとりでに逆回転しはじめた。
そしてゼロの位置で止まる。
二つ目の時計、停止。
三つ目は寝室にあった。
ベッドの上に白い服の少女が眠っていた。懐中時計を胸の上に置いて――
「ごめん、少しだけ……」
そっと手を伸ばそうとした瞬間、彼女の目が開いた。真っ黒な瞳。感情のない声で言った。
「時間を止めたいの?」
「……ああ」
「じゃあ、私の時間も止めて」
彼女は懐中時計を差し出した。針はカチコチと進んでいた。俺が手を伸ばした瞬間、少女の体が淡い光に包まれる。光が消えると、ベッドは空っぽだった。
懐中時計は冷たく、針はもう動いていなかった。まるでこの手でひどいことをしてしまったような、嫌な感触が残った。
とにかく、三つ目も停止。
残るは最後の一つ。
屋敷の屋根にそびえる大時計。螺旋階段を登りながら、息が上がる。夢の中なのに、体の疲労が妙にリアルだった。
上に着くと、巨大な歯車が唸りを上げていた。塔の中は暗く、鉄の匂いがする。
「これを止めれば……」
足元のレバーを見つけた。だが、その前に何かが立ちはだかった。
――自分と同じ顔をした何者かだった。
「止めるな」
自分と同じ声が響く。
「時間を止めたら、お前はもう目覚められない」
「何だよ、お前」
「お前の中の、目覚めたくない部分さ」
その声を聞いた瞬間、胸の奥に何かが刺さった気がした。確かに、俺は時計を止めながら時々思っていた。このまま夢の中にいれば、面倒なことは一切なくなって、むしろ楽なんじゃないかって。
「いや、でも……戻らなきゃ」
「戻ってどうする? 朝の電車、仕事、同じ日々。ここでは時間を選べる。止めるも、進めるも、自由だ」
「自由? 違うな。動かせば動くし、止めれば止まる」
「そうだ。自分の自由にできるじゃないか」
「なんか……違うんだよ」
俺はレバーを掴み、一気に引いた。
轟音。歯車が逆回転をはじめ、大時計の針がゆっくりと止まる。世界が白く光り、音も色も消えていった。
気がつくと、自分の部屋のベッドの上だった。
枕元の目覚ましが鳴っている。朝の光がカーテンの隙間から差し込んでいた。
「……夢か。夢だったんだよな」
そう呟いて、目覚ましを止めた。針は午前6時を指している。
窓の外の景色は昨日とまったく同じ。新聞の見出しも異常なし、天気予報も、カレンダーの日付も――やっぱり全部夢だったんだ。
俺は小さく笑った。
「やけに真に迫った夢だったな……まあ、いいか。今日も同じ一日だ」
しかし机の上を見ると、あの懐中時計が置かれていた。あの白い服の女の子が持っていた三つ目の時計だ。針は動かないまま、静かに光を反射している。
混乱した。間違いなく夢だったはずなのだが、夢の中の時計がここにある。
カチ、カチと。耳の奥で、もう一つの音がした。――まだ、どこかの時計が動いている。

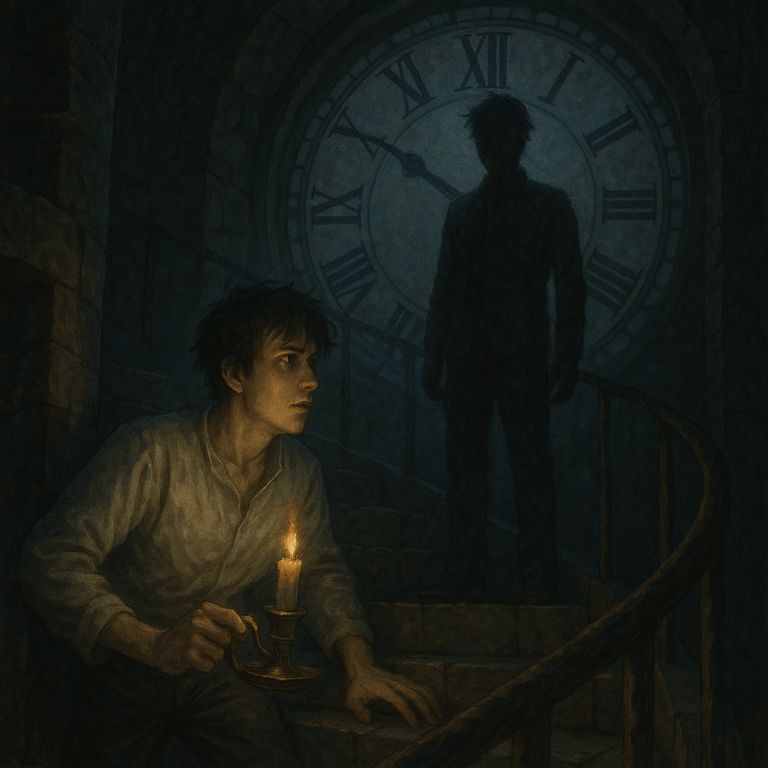


コメント