夏祭りは毎年家族で行く恒例の行事だった。
兄と私は浴衣を着て、母と三人で神社の境内に向かう。兄は射的が得意で、いつも私の分まで景品を取ってくれる優しい人だった。
けれどその夜は、兄の様子が少し違っていた。
神社の境内は大勢の人で賑わっていた。屋台の並ぶ通りで、兄がふと立ち止まったんだ。
「……誰か、呼んでる気がする」
そう呟いた兄の表情は、普段の穏やかなものとは違い、どこか虚ろだった。
「お兄ちゃん、どうしたの?」
私が声をかけると、兄は答えずにそのまま屋台の奥へ歩き始めた。
「ちょっと、お兄ちゃん!」
慌てて後を追おうとしたけど、周囲の人混みに邪魔されてすぐに兄の姿を見失ってしまった。私はこのときの兄の途切れ途切れの後ろ姿を何度も思い返すことになる。
母と私は必死になって兄を探した。けれど、兄はまるで最初から存在しなかったかのようにどこにもいなかった。
翌朝になって――兄はひょこりと帰ってきた。
けれど、明らかに違和感があった。何も話さない。質問しても曖昧な返事しかしない。食事も箸をつけるだけで、味がわかっていないように無表情だった。
その日から家の中で――いや、兄の周りで奇妙なことが起こり始めた。
まず最初に気付いたのは母だった。兄の部屋の前を通ると、ひそひそと誰かと話しているような声が聞こえるというのだ。
けれど扉を開けると、兄は一人で黙って座っているだけ。
次に気づいたのは私だった。
夜中に目が覚めると兄が廊下に立っていた。暗闇の中で無表情にこちらを見つめている。
「どうしたの?」と問いかけても兄は何も言わず、じっと私を凝視するだけだった。
そんな日々が続くうち、家族は少しずつ兄を避けるようになった。
何かがおかしい。兄であって兄ではない――そんな疑惑が私たちを苛んでいた。
ある晩、私は真夜中に物音で目を覚ました。
音のする兄の部屋の前へそっと近づき、隙間から覗き込むと――。
そこには兄と、もう一人、黒い影のようなものが向かい合っていた。影はゆらゆらと揺れながら、兄の耳元で何かを囁いているようだった。
「……もう少しで……入れ替わりが……」
その言葉を聞いて、私は震えが止まらなくなった。
兄は影に向かって頷いていた。兄の表情は、無表情から次第に喜びの混じった不気味な笑みへと変わっていった。
私は怖くなって自分の部屋に逃げ戻った。何かが兄を、私たちから奪おうとしている。そんな気がして、私は兄をよく観察するようになった。
兄は日を追うごとにやつれ、私たちに対して無感情なままだった。そして、隠れて影と何かを話し続けていた。
そして数日後、夜中にふと目を覚ますと、兄が私の枕元に立っていた。
「ねえ、気付いたんだろ?」
兄の顔は微笑んでいるようだったけど、その笑顔に感情は感じられなかった。
身体は動かず、ただ恐怖で固まっている私に、兄は低く囁いた。
「心配しなくていい。君のお兄ちゃんはもうとっくにいないけど、すぐに慣れるから……」
兄が手を伸ばしたその瞬間、部屋の窓から青白い月光が差し込み、兄の背後にあの影がくっきりと浮かび上がった。影の正体ははっきりとはわからないけれど、どこか兄に似ている。
「もうすぐだよ……君も僕たちの仲間になれる」
影の声は、兄の声と完全に重なって聞こえた。
翌朝目覚めると、兄の姿はなかった。母も「兄は最初からいなかった」と言い張る。まるで、兄という存在が家族の記憶から消されてしまったかのように。
けれど私は覚えている。兄が夏祭りの夜に消え、その後戻ってきたのは別の何かだったことを……。そして、あの影がわずかに残った兄の残滓までをも完全に連れ去って行ったことを。
今もたまに、家の廊下で兄の声が聞こえる気がする。
私を呼ぶ、優しかったあの本当の兄の声が。
だけど振り返る勇気はない。もし振り返れば、そこにいるのはきっと――。


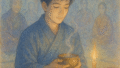
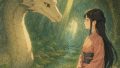
コメント