残業につぐ残業。しかし労働環境がブラックといわれると、そこがすごく曖昧だ。
有給は頑張ればなんとか取れる。上司は厳しいが、ぎりぎり常識の範囲内。ただ、人手不足なのか、残った人員への仕事は日に日に増えていく。
いっそ笑えるくらいのブラックな環境であれば、SNSでネタにしてすっきり辞めることができるのだが……。
その日、会社のエレベーターを降りた瞬間、目の前に広がっていたのは見慣れたオフィスのロビー――じゃなかった。
いや、これは一体どこなんだ?
残業が続いた日の帰りだった。ビルの10階からエレベーターに乗り込み、いつも通りロビーへ向かったつもりだった。扉が開く音とともに一歩踏み出した瞬間、空気が変わったのを感じた。
ロビーのはずなのに、目の前に広がっていたのは見たこともない風景。夕陽に照らされた赤い砂漠が広がり、風に舞う砂が頬に触れる感覚まであった。耳には鳥の鳴き声のようなものが聞こえるが、見渡しても生き物の気配はない。
「……どういうことだ?」
混乱して振り返ると、そこにエレベーターはない。ただ広大な砂漠広がり、戻る道が消えていたんだ。
仕方なく砂漠を歩き出した。すると、少し離れた場所に木のようなものが見えた。けれど近づいてみると、それは木ではなく、巨大な金属の柱だった。表面には奇妙な文字が彫られていて、それを見た瞬間、頭の中に直接声が響いた。
「ここにいてはいけない。ここは君の世界ではない」
声の主を探すが、周囲には誰もいない。ただ果てしなく赤い砂漠が広がるばかりだ。
途方に暮れながらも歩き続けると、突如として前方に小さな建物が現れた。
砂丘の陰から突然に姿を現したそれは、見たこともないような奇妙な構造をしている。
扉を押し開けると、中には年老いた男が一人、背を向けて立っていた。
「待っていたよ」
男がゆっくり振り返る。その顔には優しい笑みが浮かんでいた。
「ここはどこなんですか? どうやって戻れば……」
男はゆっくりと椅子に座り、私に座るよう手招きした。
「焦らずに聞いてほしい。君がいた世界とこの世界は隣り合って存在しているんだ。ほんの少しの偶然で繋がってしまうことがある」
彼が語るところによれば、この世界は無数にある世界の中でも境界の曖昧な場所で、時折私のような迷子が迷い込むのだという。
「元の世界に帰れるんですか?」
彼はうなずき、続けた。
「可能だ。ただし、帰るためには一つだけやってもらわなければならないことがある。それをやり遂げれば、元の世界へ戻れる扉が開く」
「その一つのこととは?」
どんな難しい難題が突きつけられるのかと、私は息を呑んで問いかけた。
「君自身の問題を解決させなければならない」
その意味が理解できずに黙っていると、彼は微笑みながら立ち上がり、小さな瓶を差し出した。
「この砂漠の砂を、この瓶いっぱいに満たすことができたら、扉は再び現れる」
簡単そうで拍子抜けする。
私は瓶を受け取り、すぐに外へ出て砂を詰め始めた。
ところが、いくら砂を詰めても瓶は一向に満たされない。瓶の底には確かに砂が入っているのに、増える気配がないのだ。
疲れ果て、再び老人の元に戻った。
「砂がたまらないんです。どうしてでしょう?」
老人は静かに言った。
「それは君が、本当に戻りたいのか確信を持てていないからだ。君の心が迷っている限り、瓶は満たされない」
彼の言葉を聞き、なるほどと思う。
心のどこかでこのままなら、とりあえず仕事に行かなくて済むぞと思っていたところはある。
ここにいたいわけではないが、自分が思っていた以上に仕事に行きたくないらしい。
私は初めて自分の内側を見つめはじめた。自分は一体何をしたいのだろう。
子供の頃になりたかったのは何だっただろう……。子供の頃の自分が、今のこの姿を見たら何と思うか。
――戻って、すべて立て直さなければならない。
深く息を吸い、再び砂を瓶に詰め始める。今度は瓶が見る見るうちに砂で満ちていくのが分かった。
瓶がいっぱいになった瞬間、辺りの景色が揺らぎ始め、目の前にあのエレベーターが現れた。
「さぁ、行きなさい」
老人が頷いた。
私はエレベーターに駆け込むと、急いで閉じるボタンを押した。再び扉が開いた瞬間、目の前にはいつものロビーの風景が広がっていた。
翌日、私は会社に辞表を提出した。
だが今でも時折、夕陽を眺めていると、あの赤い砂漠の匂いがよみがえることがある。そのたびに老人の言葉を思い出し、世界への感謝を噛み締めるのだ。

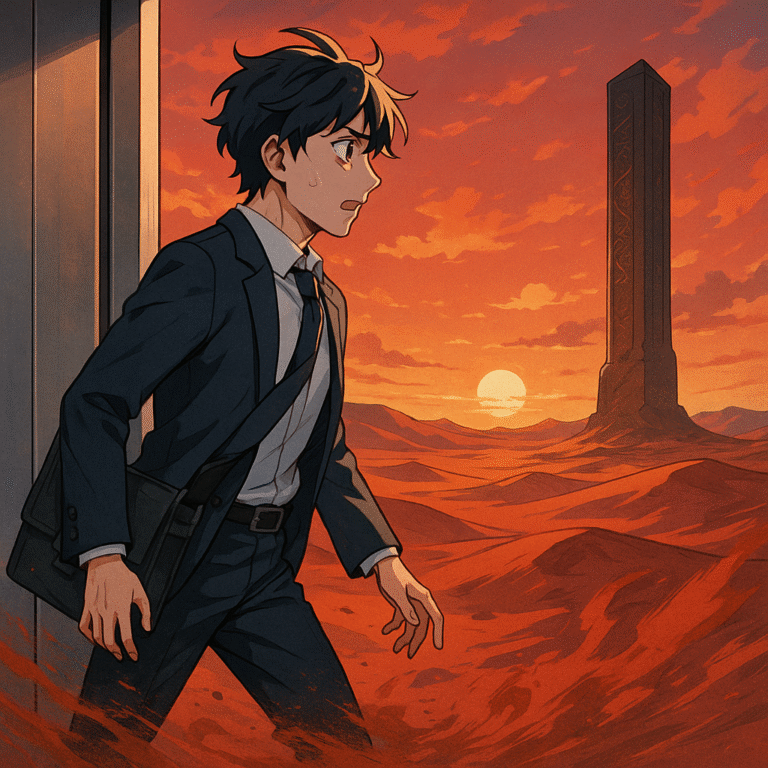


コメント