夜が更けるほどに、私は本の世界に没頭していた。
読み進めても読み進めても、物語は終わらない。奇妙な予感が胸をよぎる。
古書店で偶然見つけたその本は、表紙に「物語は繰り返される」とだけ書かれていた。
著者名も出版社も記されていない、不気味なほど無機質な装丁だった。それでも手に取らずにはいられなかったのは、その文字にどこか引き寄せられたからだろう。
家に帰り、ページを開いた瞬間から、物語の虜になった。内容は一人の旅人が迷い込んだ街で奇妙な出来事に巻き込まれるというものだった。
旅人は街を出ようとするが、出口はどこにも見つからない。街の住人たちは皆、微笑みながら「ここを出る方法など知らない」と言うばかり。
読み始めて数時間、私は疲れを感じてふと時計を見た。すでに深夜3時を過ぎていた。そろそろ休もうと本を閉じようとしたが、指がページから離れない。まるで本そのものが私の手を引いているようだった。
続きも気になるし、もう少しだけと、読み続ける。物語の旅人は街の中央にある大きな時計塔を見つけた。その時計塔の周りを人々がぐるぐると回り続けている。旅人が「何をしているんだ?」と尋ねると、人々は「時間を回している」と答える。
私はこの場面に妙な既視感を覚えた。どこかで同じ光景を見た気がするのだが、どこでだろうか。いや、時計塔の周りを人が回るなんて光景、ちょっと現実的ではない。何かの映画だろうか。思い出そうとすると、頭の奥がちりちりと熱を帯びてくるようだった。
物語の旅人は街の人々から次第に避けられるようになった。誰も彼に目を合わせようとせず、ただ時計塔の周囲を回り続けている。旅人が苛立ちながらも街の中心部を離れようとすると、なぜか元の時計塔前に戻ってしまう。
ページをめくるたび、現実の感覚が薄れ、物語の世界と自分が混ざり合っていくようだった。息苦しさを感じ始めて、再び本を閉じようとするが、また本から手が離れない。体はまるで私の意思に反するようにページをめくり続ける。
物語の旅人は絶望の中、時計塔に登り始めた。階段を上るたびに自分が歩いてきた街の景色が違うものに変わっていく。やがて彼は時計塔の最上階に辿り着いたが、そこには扉が一つあった。
扉を開けると、その先には旅人が最初に街に入ってきた入り口が見えた。戻る道を見つけたと思い、彼は勢いよく駆け出した。だが、その入り口を抜けると再び街の中央、時計塔の前に戻ってきてしまったのだ。
私の心臓は激しく打ち始めていた。このままでは自分も旅人と同じように、この物語から抜け出せなくなってしまう気がしてならない。無理やり力を込めて本を引き離そうとしたが、指は一向に動かない。
「逃げられないよ」
指が勝手にめくったページの最初にそう書いてあった。それは旅人へ向けたセリフだったが、旅人ではなく、私自身に向けて話しかけているように見える。
さらにページをめくる。
「この物語は読む者がいなければ完成しない。君がこの街を出るには、読む者が最後までページをめくり続ける必要がある。しかし、ページがめくられることにより、我々は存在し続け、君はここを出ることを妨害される」
私は声にならない悲鳴を上げたが、指は頑なに本から離れない。
気がつけば、私は時計塔の前に立っていた。自分が本を読んでいる現実は遠くなり、目の前には物語の世界が広がっている。周囲の住人たちは時計塔を回りながら私に微笑んでいる。
「ようこそ。物語が繰り返される」
旅人はどこにもいなかった。そこに立っているのは私一人だ。
私は時計塔を見上げながら悟った。この物語は決して終わらない。私が出口を見つけられない限り、永遠に繰り返される。
「物語は繰り返される」
本の表紙に記されたその言葉が、時計塔の鐘の音と共に頭の中で鳴り響いていた。


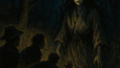

コメント