目を開けると、石の天井があった。
ひんやりとした空気と、かすかに漂う鉄と苔の匂い。
私は、なぜここにいるのかも思い出せないまま、立ち上がった。
四方を囲むのは、重厚な石の壁。
奥へと続く一本の通路があり、私は迷うことなくそこを歩き出した。
歩き続けるたびに、道は分岐し、また繋がり、階段や扉、橋や回廊が現れた。
まるでこの迷宮全体が、生きて呼吸しているかのようだった。
私は誰なのか。なぜこの迷宮にいるのか。その問いを自分に投げかけながら、私は進み続けた。
通路の途中、錆びた鉄格子があった。
向こう側には誰もいない。だが、格子の隙間から、どこか懐かしい声が聴こえた気がした。
「こっちへおいで」
私は引き寄せられるように扉を開けた。
扉の先は小さな中庭で、中央に古びた噴水があった。その水面に映る自分の顔を覗き込むと、見知らぬ誰かがそこにいた。だが、その目だけは、どこか遠い記憶に触れる気がした。
迷宮を進むうち、時間の感覚は薄れ、昼も夜も分からなくなった。時折、壁に刻まれた奇妙な模様や、不思議な詩の断片が目についた。
『ひとつの声は、ふたつの影、ふたつの扉は、みっつの出口』
それは誰が刻んだのか分からないが、どこか導きのようにも思えた。
さらに進むと、壁に沿って古びたランタンが灯っていた。炎は消えかけていたが、どこか温かさを感じる光だった。
やがて広い広間に出た。
中央には円卓があり、そこに何人かの人影が座っていた。
みな顔を伏せ、言葉も交わさない。私が近づくと、ひとりの老人がゆっくり顔を上げ、低い声で言った。
「出口を探しているのか」
私は頷いた。
老人は手を伸ばし、私の肩に触れた。
「この迷宮に入った者は皆、自分を探している。
出口は一つではない。
どの扉も、お前が進んだ道の先にしか現れない」
私は出口について尋ねた。老人は静かに微笑んだ。
「出口は必ずある。ただし、それが“帰る場所”とは限らない。お前が何を求めてここに辿り着いたのか、それを思い出したとき、道は開かれるだろう」
私は円卓を離れ、再び迷宮の奥へと歩き出した。
進むほどに道は入り組み、行き止まりに見えた扉が不意に開いたり、元いた場所に戻されたりもした。
不意に、壁の隙間から音楽が聞こえてきた。懐かしい子守唄のような旋律だった。音のする方へ歩くと、小さな部屋に辿り着いた。
そこには少女が一人、ひざを抱えて座っていた。彼女は私に気づくと、静かに微笑んだ。
「出口を探してるの?」
私は頷いた。
少女は少し首をかしげた。
「じゃあ、一緒に探してあげる」
少女と歩くうちに、不思議と心が落ち着いた。
迷宮は次第に明るくなり、温かい風が通り抜けていく。
やがて目の前に三つの扉が現れた。
一つは赤い扉、一つは青い扉、もう一つは白い扉。
「どれを選ぶ?」
少女は私に微笑む。私は少し迷ったが、白い扉を選んだ。
扉を開けると、そこには草原が広がり、眩しい光が降り注いでいた。私はゆっくりと草原を歩いた。
ふと振り返ると、少女は扉の前に立ったまま、手を振っていた。
「さよなら。また会えるよ」
光の中を進むうち、私は自分の名前や過去、そしてここに来た理由を思い出し始めた。
私は迷宮に迷い込んだのではなく、自ら選んでここに来たのだ。心に傷を負い、現実の痛みから逃げ出すために。
出口を探す旅は、実は自分自身を探す旅だった。
草原の先で、大きな一本の木が見えた。その木の下にたどり着いたとき、私は静かに目を閉じた。
温かな風と、あの子守唄のような音楽に包まれて。
やがて再び目を開けると、もうそこに迷宮はなかった。私の前には、広くて穏やかな世界が広がっていた。
迷宮のうたが、私を静かに送り出してくれたのだ。
私はゆっくりと歩き出した。もう、何も迷うことはなかった。

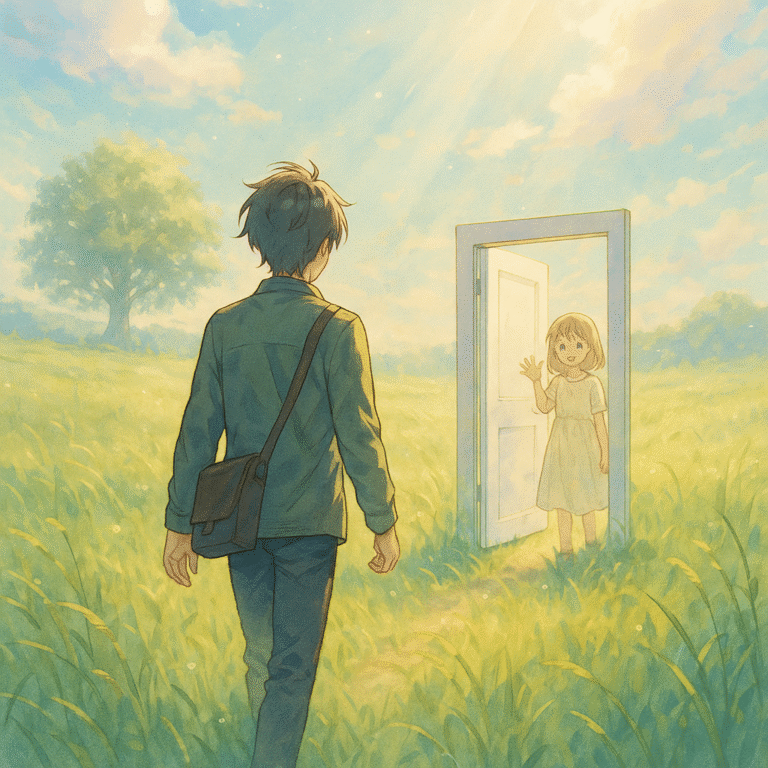
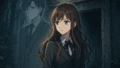

コメント