すべては仕事帰りの夜だった。
今日は妙に体が重かった。コンビニでビールでも買って帰ろうか――そう考えながら、駅から家までの道を歩く。湿った夜風が頬にまとわりつき、足取りは自然と遅くなっていた。
そのとき、通りの向こうで何かが動いた。薄暗い街灯の下、二つの影が絡み合っている。喧嘩か?
「大丈夫ですか」と声をかけようとした、その瞬間、全身に寒気が走った。
しがみついていたのは、人間ではなかった。皮膚は爛れ、濁った目は焦点を失い、口元から赤黒い液体を垂らしている。喉の奥で獣のような音を漏らし、しがみつかれた人物の首元に顔を埋めていた。
「……いやいや、ありえない」
現実では起こり得ない光景。映画でしか見たことのないゾンビ。そう否定しながらも、目の前の生々しさは、理屈では片付けられない。
噛みつかれていた人物が、電池が切れたように一切の抵抗をやめてぐったりとした。そしてこちらを振り向く。その虚ろな目が、まっすぐ俺を射抜いた。ゾンビになってる!
――逃げろ。
足が勝手に動き、路地を全力で駆け抜けた。
振り返ると、複数のゾンビがこちらへ向かってくる。喉が焼けるように苦しい。やがて同じように逃げている人々が合流してきた。
「スーパーマーケットに逃げ込め!」
誰かの叫びに従い、巨大スーパーマーケットへ飛び込む。自動ドアが開く音がやけに軽やかに響く。無事な人間みんなが駆け込み、振り返りざまに商品棚やカートを押し付け、ドアを塞ぐバリケードを作った。みんなゾンビ映画は見たことがあるらしく、誰に指示されるわけでもないのに、他の入口を確認して塞いだりしていた。
外ではゾンビたちがガラスを叩き続けている。
「……まるで映画みたいだな」
誰かが呟いたが、笑う者はいない。
ここに逃げ込んだ人数は八人だった。会社帰りらしきスーツ姿の真中さん、美作さん、買い物途中だった主婦の佐藤さん、老紳士の松本さん、大学からの帰りに追いかけられたカナちゃん、そしてスーパーのパート店員の三浦さん、吉田さん、迫田さん。
スマホを開くが、パニック映画のお約束通りの「圏外」だった。
当然ニュースも更新されないので、何が起こっているのか見当もつかない。老紳士の松本さんが静かに言った。
「こういうときこそ冷静に。水や食料の確認を」
店内の物資はもちろん豊富だった。だからスーパーマーケットに逃げ込むのがセオリーなのだ。
パン、カップ麺、ペットボトルの水、缶詰などの食料はもちろんのこと、生活雑貨や水道、トイレも完備されている。まさにうってつけの立てこもり場所だ。
しかし、この異常事態がいつまで続くのかは誰にも分からない。慎重に管理していかなければならない。
夜が更けるにつれ、外のゾンビは増えていった。ドアを叩く音は重く鈍く、びしゃびしゃと濡れた音がして気持ち悪い。しかし、何かを必死に訴えているような様子がして気になった。
一人がぼそりと言った。
「どうして俺たちだけ生き残ったんだろう」
「偶然だろ」
「……本当? 他の人は全員ゾンビになっちゃったよ?」
答えられる者はいなかった。
そのとき、非常灯がチカチカと点滅し、薄暗い店内の奥に人影が立っていた。
「誰か入ってきたのか?」
美作さんが声を震わせる。
「バリケード動いてないはずだ……さっき点検したばかりなんだが」
主にバリケード関係を仕切ってくれていた真中さんが声をあげた。
人影はゆっくりと近づいてくる。
スッ……スッ……と床を滑るような足取り。照明がちらつくたび、その輪郭がぼやける。誰も見覚えのない顔。痩せ型の大人しそうな顔立ちをした青年だった。
ゾンビでないことにホッとしながらも、パートの三浦さんが恐る恐る声をかける。
「あなた……どこから入ったの?」
答えはない。ただ、ガラス玉のような目で俺たちを見つめる。その視線に、背中の毛が逆立つ。ゾンビの目つきにそっくりだ。
大学生のカナちゃんが小さく言った。
「あ、あの人の足、床についてない!」
見れば、本当に青年の足は床から数センチ浮いている。
その瞬間、外のゾンビが一斉にガラスを叩き始めた。ドン、ドン、ドン――。
その音はなぜか、店内の照明の点滅と同期している。
「もう遅いよ」
青年が囁くように言う。やがて、スーパーの店内BGMが突然流れた。
「本日はご来店ありがとうございます。当店はまもなく閉店いたします……」
流れ出す蛍の光。時刻は午前三時。そして照明がすべて落ちた。
闇の中、足音が増えていく。急に辺りに立ち込める腐臭。
女性たちの悲鳴が次々にあがった。外にいたはずのゾンビたちが、いつの間にか店内に入ってきている?
次に灯りがついたとき、ガラス戸の向こうは真っ白な霧に覆われていた。外の景色はどこにもない。てっきりゾンビに囲まれていると思っていた俺たちは、呆然と立ち尽くしていた。
その霧の前に、さっきの青年が立っている。
「みなさん、久しぶりですね」
青年は微笑んだ。
美作さんが震える声で聞いた。
「お前は……誰なんだ」
「ここにいるみんな、僕に親切にしてくれたことがある。でも、覚えていないでしょう?」
言われた瞬間、脳裏に映像が流れ込んできた。
――会社帰りに駅前で具合が悪そうに座り込んでいた青年に「大丈夫?」と声をかけた。ちょっと休めば問題ないと言ったので、近くの自販機で水を買って渡した。それだけのことだ。
小さな親切の記憶。しかし、それがなんだと言うのだろうか。
周りの人々も、何かを思い出したような顔をしている。
青年は穏やかに告げた。
「僕は自殺しました。けど、親切にしてくれたみなさんのこと、忘れられなかったんです。あのときは本当にうれしくて、ずっと一緒にいられたらいいなと思ったんです」
周りの全員がハッと息をのんだのを感じた。
これまで見たものが一気に逆転した。ゾンビはすべて幻覚だ。現実にあった映像が一気に脳内に流れ込んでくる。
今まで怯えていたゾンビたちの方が、現実に生きていた人間たちで、必死に俺たちがここにとどまるのをやめさせようとしていた。その中には家族もいた。きゅっと喉が鳴り、涙が一筋こぼれる。
もう、すべてが遅かった。
霧の奥から、暖かい光が差し込む。
「安心して。ここでは誰も飢えず、怯えず、争わない。一緒にいてさえくれればいい」
俺たちは観念したように、光の方へと歩み出す。もう道はそちらしかなかった。


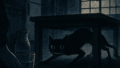

コメント