少年がそれを拾ったのは、戦場の外れだった。
瓦礫と灰に覆われた大地の隅、泥に半分埋もれるようにして転がっていた古びた木箱。蓋を開けると、中には色あせた絵の具が並んでいた。
赤、青、緑、黒。
ただそれだけ。
しかし、どの色も普通の絵の具とは違う、奇妙な輝きを放っていた。
少年は戦争孤児で、絵の具の使い方も知らなかった。だが、その日、無性に何かを描きたくなった。
近くにあった瓦礫の破片をキャンバス代わりにして、赤を指に取り、力任せに線を引いた。すると、瓦礫が突然、赤々と燃え上がったのだ。
慌てて手を放す。今度は青を塗り重ねてみた。
炎は一瞬で水蒸気に変わり、辺りに雨のように降り注いだ。
驚きと同時に胸の奥で何かがざわついた。
「これは……武器だ」
やがて少年は絵の具を持ち歩くようになった。赤は火を生み、青は水を呼び、緑は風を操る。
そして黒――それだけは、不気味な気配を放っており、少年は使うのをためらっていた。
ある夜、少年たちの隠れ家に敵兵が迫ってきた。追い詰められた少年は、恐怖のまま黒い絵の具を手に取った。
すると、足元から影が立ち上がり、敵兵たちを次々と飲み込んでいく。声もなく、跡形もなく。そして影の中に引きずり込まれた彼らの姿が、二度と現れることはなかった。
少年は震えながらも、絵の具を握りしめた。
「黒は……消す色なんだ」
その日から、彼は絵の具を使って戦場を渡り歩いた。
仲間を守るために火を描き、喉の渇きを癒すために水を描き、避けられない爆撃を風で逸らす。
人々は彼を「絵の具の戦士」と呼んだ。
やがて少年は一人の将軍の前に立たされた。
「その力を、我らのために使え」
だが少年は首を振った。
「これは戦うためのものじゃない。生きるために描くんだ」
将軍は冷笑し、兵を差し向けた。
その時、少年はためらわず黒を塗った。将軍と兵士たちは影に呑まれ、消えた。戦場に静寂が訪れた。
その夜、少年はふと気づいた。
前は黒い絵の具を使うことにためらいがあったが、今はどうだろう。いとも簡単に人間を消してしまった。
自分の影が、前よりも濃く、長く伸びている気がした。まるで黒の絵の具に引きずられるように。
胸の奥に重い不安が沈んだ。それでも絵の具を手放せなかった。
ある時、仲間の少女が泣きながら訴えた。
「お願い、父さんを助けて。戦場に行ったきり帰ってこないの」
少年は迷わず、瓦礫に父親の姿を描いた。赤で体温を、青で涙を、緑で息吹を。そして最後に黒を混ぜた。
こういう使い方ができることを、少年は体で学んでいた。もはや絵の具は体の一部のようになっている。
やがて完成した絵から、人影が立ち上がった。
それは少女の父親だった。
「……本当に、父さんだ」
少女が抱きつくと、その体は一瞬にして崩れ、影となって消えた。
絵の具は幻を生み出せても本物を生み出すことはできない。
少年はその夜、黒を睨みつけた。
「お前は奪うばかりだ」
黒い絵の具は少年の言葉を肯定するかのように脈打っていた。
戦争は終わらなかった。日々、仲間が倒れ、家が崩れ、未来が失われていった。少年は必死に描いた。描いて戦った。
火で敵を退け、水で命を繋ぎ、風で敵兵をなぎ倒す。
だが描けば描くほど、なぜか黒が混ざり込んでくる。ある日、気づけばキャンバスに広がったのは黒ばかりだった。
「……俺は何を描いているんだ」
次の瞬間、地平線が黒く塗り潰された。空も、大地も、すべてが影に覆われていく。少年の足元から、自分自身の影が立ち上がった。
それは、少年の姿をした「もう一人の存在」だった。
「運命は塗り替えられる。だけど、色を選んでいるのは本当に君か?」
影の少年が問いかける。木箱の中には赤も青も緑も消えていた。
残されたのは、黒だけ。
少年はゆっくりと筆を握った。
「なら、最後まで描くさ。影に飲まれてでも。生きなきゃならないから」
その一筆が、大地をさらに塗り潰していく。
やがて影に包まれた世界は、不思議な静けさを取り戻した。戦争は終結した。少年の手により、すべてを塗りつぶす形で――
黒い世界の中で、少年は筆を置く。
――そこにはまだ、描かれていない余白が残っていた。


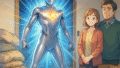

コメント