深夜二時、携帯の留守番電話に非通知の着信履歴が残っている。
最初の1、2回は気にも留めなかった。
「間違い電話だろう」
そう思って履歴を削除した。
だが、それは毎晩、同じ時刻に繰り返される。
留守電も残っており再生してみると、録音されているのはただの沈黙。
無言のまま、数十秒――そして、ぷつりと切られる。
けれど、不気味なのは、そこに誰かがいる気配がすることだ。まったくの無音というよりは、電話口の向こうで何か動いているような……?
誰かが電話番号を間違えているのだろうか。最近はあまり聞かないが、ポケットに入れておいた携帯が誤動作して電話をかけてしまうトラブルはある。
いずれにしろ大した問題ではないだろう。
だが着歴が残り続けて五日目を過ぎた頃には、夜になるのが恐ろしくなっていた。
私はとうとう、親しい友人の健司に電話で相談した。
「なあ……深夜二時に必ず無言電話が入るんだ」
健司は黙り込んでいる。言葉を探しているような沈黙が流れた。
「なぁ、雄也。お前……いや、どういうことだ?」
「ただの無言電話なんだけど……誰かがこっちの様子をうかがっているみたいで気持ち悪いんだ」
しかし、健司の様子もおかしかった。話をちゃんと聞いているのかわからないが、黙りがちだ。
「……悪戯じゃないのか? お前、本当に――」
私は声を潜めた。
「でもな、何かを伝えようとしてる気がするんだ」
健司は黙ったまま、それこそこちらの様子をうかがっているかのようだ。
「健司、まさかお前が?」
「今、どこにいるんだ?」
健司は声を震わせる。
「は? 家だよ」
「あのな、お前――」
そのとき、また二時が近づいていることに気がついた。
「健司、もうすぐその電話がかかってくるかもしれないからいったん切るよ。録音して後で聞かせるから」
液晶に「1:59」と表示されたとき、心臓が異様に大きく鳴り始めた。
次の瞬間、携帯が震えた。
画面に「非通知着信」の文字。
息を詰めながら、通話ボタンを押し、すぐに録音も開始する。
……静寂。
けれど、やはり無音ではない。
耳を澄ますと、留守電では聞き取れていなかった男――重い「何か」がこちらに迫ってくるような微かな物音がした。
聞いているだけで心臓が圧迫されるような気配――思わず声を出してしまう。
「……おい、聞こえるか?」
それに返事はなかった。
ずずっ……ざっ、ずっ……。
ただの雑音ではない。何かが這うような音。手が震えはじめる。
この音、まさか……。
その瞬間、フラッシュバックするように過去の記憶が閃いた。
ずずっ……ずっずっ。
何かがこちらに近づいてくる。
「……けて、……たすけ……」
思わず携帯電話を取り落とした。しかし、落下の衝撃音は聞こえなかった。――部屋の中は真っ暗だ。
しかし俺はあの日の出来事を思い出してしまっていた。いや、これまで何度も思い出していたのだ。また忘れ、また繰り返す……。
「――雄也? いるのか?」
突然、部屋のドアが開いた。健司だ。健司は携帯のライトを頼りにきょろきょろしながら部屋へと入ってくる。
「さすがに電気は止まってるのか」
照明のスイッチをカチカチと連打しながら舌打ちをする。
「こういうとき、どうしたらいいのかわからん」
健司は部屋の中でどかっとあぐらをかいた。
「雄也、お前がここにいると思って端的に話すぞ。お前は1ヶ月前にバイク事故で死んだんだ。ちょうど午前2時頃だ。時間は医者の見立てだが。お前、夜中にひとりで走るの好きだったよなぁ。でもそれで……目撃者がいなくて通報が遅れた」
健司はエコバッグからスミノフアイスを2本取り出し、床に置いた。
「こういうときはお神酒とかのがいいのかもしれんが、お前とよくこれを飲んだよな」
そういうと、瓶の蓋を開けて飲み始める。お神酒は神社じゃないのか?
「線香とかのがよかったか?」
『冗談はよせよ』
俺はもう1本のスミノフアイスに手を伸ばす。しかしするりと手がすり抜けた。まるでそれが見えていたかのように、健司がその瓶の蓋も開けてくれる。
「まぁ、なんだ。いろいろと無念かもしれんが、ここにいても仕方ないんじゃないか。いや、実は俺もよく知らんが」
『知らないくせに適当なことを言うなよ』
俺は思わず笑った。
まるでその笑い声が聞こえたかのように健司がハッと顔をあげた。
「なんか――やっぱりいるんだな。見えないけど、いるよな、お前! ここに! あ、いや、ちょっと酔ったのかな」
健司は急にしゅんとうなだれると、黙ってちびちびと酒を飲み続ける。
よく走りに行った山道、ライトに照らされたアスファルト、飛び出してきた何かわからない小動物、ブレーキ音。
その瞬間、記憶は一度途切れていた。
――そうだ。
あの無言電話。沈黙の向こうで、俺はずっと助けを待っていた。そして最後の力を振り絞って放り出されてしまった携帯電話に手を伸ばしていた――が、おそらく届かなかったのだ。
その無念が自分自身がかけようとしていた電話を受け続けるという煉獄を生み出していたのだ。しかし今日、健司がそれを断ち切ってくれた。
『本当にありがとう、健司。俺、もう行くよ』
もう一度スミノフアイスに手を伸ばすと、すっきりとした甘みが口に広がった気がした。思い残すことは山ほどある……それでも、人生ってこういうものなんだろうな



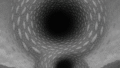
コメント