コピー室の斉藤。
うちの会社で彼を知らない人間はいない。
どんなに面倒な資料でも、彼に頼めば数分で完璧に仕上げてくれる。しかもミスゼロ。
パンチ穴の位置、ステープラーの角度、用紙の混在――全部、彼の中に設計図でもあるかのように的確。
「斉藤くん、コピーお願い!」
「はい、原本は何ページですか? 両面でいいです?」
「うん、それで。あ、最後に資料全部、3ページ目と15ページ目にこの付箋も貼っておいてもらえる?」
「了解です」
そんな感じで、いつの間にか彼はコピー室の主になった。
もともと彼は営業部だった。
だが、几帳面すぎる性格が災いして、現場よりも資料作りにばかり時間をかけるタイプだった。
上司があきれて、嫌味まじりに「お前、いっそコピー室に詰めてろ」と言ったのを素直に真に受けて、翌日から本当にコピー室にこもり始めた。
それ以来、彼はほとんどの時間をそこで過ごしている。
朝から晩まで、紙と機械とだけ会話しているような男だ。
「コピー室の斉藤」は、半ば伝説だった。
社内ネットワークには「斉藤さんに頼んだら資料が1.3倍きれいになって返ってきた」とか、「紙詰まりすら起きない奇跡の手」とか、もはやコピー機に関しては神格化すらされている。
だけど、ある日、ふと気づいたんだ。斉藤がいつ休んでいるのか、誰も知らない。気づくとすでにコピー室にいるし、昼食時間も出てこない。退勤しているところに出くわしたこともなかった。
その日、俺は夜遅くまで残業していた。
オフィスは静まり返り、フロアの照明が半分落とされていた。ふとトイレに立った帰り、コピー室の前を通りかかった。
――光が漏れていた。
時間はすでに夜の十一時。残っている社員は俺だけのはずだ。
「まさか……斉藤さん、いるんですか?」
ドアを少しだけ開けると、かすかに機械音がした。ガシャコン、ガシャコンと、一定のリズムで紙を吐き出す音。
斉藤がいた。
コピー機の前で無言のまま、次々と紙をセットしている。でも、その様子が、なんというか――普通じゃなかった。
手の動きはよどみなく、異様に速い。紙を取って、差し込んで、ボタンを押して、終われば次のコピーへ。その一連の動作が、まるで機械のように正確だ。
「こんな時間まで作業してるんですか、斉藤さん」
思わず声をかけた。すると、動きがぴたりと止まった。
「……ああ、東堂くん。まだ残ってたんだ」
「いや、帰ろうとしてたんですけど……音がしたので」
斉藤はゆっくり振り向いた。目の下に深い隈。でも、その目は妙に澄んでいた。
「コピーだよ。明日の朝までに必要な資料があってね」
「いや、でもこんな時間まで残業してやらなくても……」
「納期は納期だから」と笑った。けれど、なんだか不自然な笑い方だ。まるで機械のような……。
「機械はいいよね」
彼は静かにささやいた。
「ただ人間の言う通りに決まったことをすればいい。間違いがあったとしても、それは人間の方に落ち度があるんだから」
そう言って、コピー機の上を優しく撫でた。
「そういえば不思議なんだ。最近、この機械の方が俺より先にボタンを押すんだよ」
目が――澄んでいる。冗談に聞こえなかった。
それから数日後。
朝、出社したらコピー室の前に人だかりができていた。中に警察がいるらしい。
コピー室といったら斉藤さんだ。しかし彼の姿は見えない。
「斉藤さんはどうしたんですか?」と同僚に聞くと、彼女は青ざめた顔で答えた。
「斉藤さん、いないの。でも……コピー機がずっと動いてて……」
見てみると、確かに機械は稼働していた。紙を吐き出し続けている。しかしそのコピー機は見たことがない機種だった。
「こんなコピー機、ここにありましたっけ?」
警察が止めようとしても、電源が切れない。ケーブルを抜いても、バッテリーのようなものが内蔵されているらしく、延々と動き続けていた。
上司は顔をしかめて、「壊れたんだろう。すぐに新しいコピー機に交換しよう」と言った。
警察官の「行方不明になった方と最後に話された方はどなたですか」という呼びかけに、「――斉藤さんがコピーのこと以外で誰かとしゃべってるところ、見たことないよね」と、誰かのささやき声が聞こえた。
翌週。
新しいコピー機が設置された。古いコピー機は撤去されたが、あの見たことがない機種は置かれたままだ。会社の所有物である証明の管理ナンバーが見当たらず、処分もできない状況だったらしい。
奇妙なことは続いた。
新しいコピー機も――勝手に動き出す。夜中に印刷が始まり、朝になると山のように資料が出来上がっている。
それが全部、完璧なレイアウトで製本されていた。しかも、表紙の右下に必ずこう書かれた付箋が貼られている。
【コピー室 斉藤】
俺は怖くなって、あの夜のことを話した。でも、誰も信じなかった。
上司は「仕事を放って失踪するようなやつ、ろくなことはない」と言って顔をしかめた。
……でも、斉藤はもしかしてまだコピー室に詰めているのではないか。あの見たことがない機種のコピー機は……。
時々、夜の残業中に聞こえるんだ。コピー機の奥から、かすかな囁き声が。
「紙の重さは、今日は75グラムだな……湿度、38%……インクの乗りは良好」
それは、確かに斉藤の声だった。
そして、コピー室のランプがゆっくり点滅する。まるで返事をするように。
――今夜も完璧な彼の稼働が始まる。

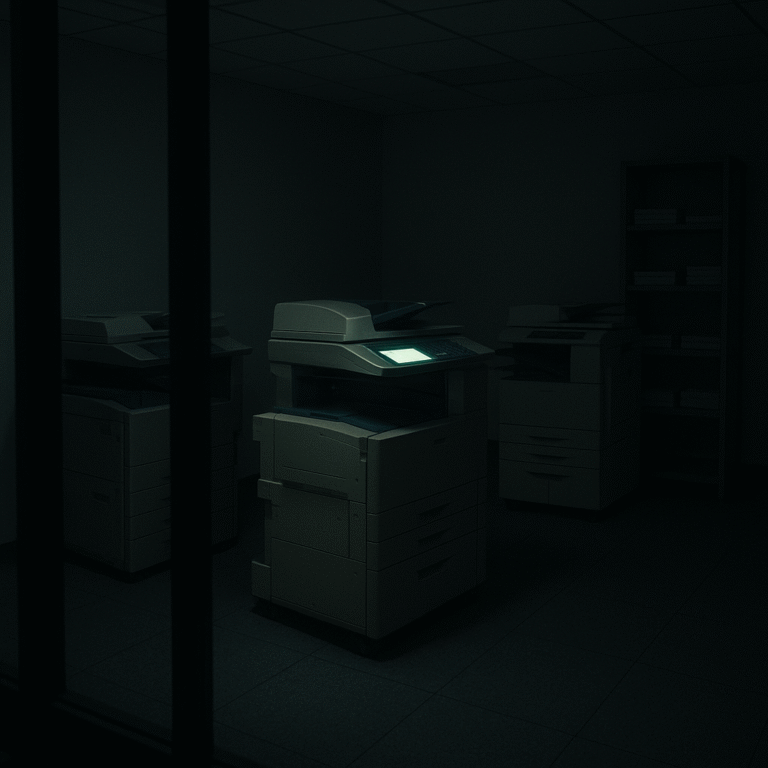

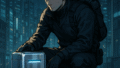
コメント