あの日、教室のドアが開いた瞬間、空気が変わった。
転校生の悠木さん。
その瞬間、ざわめきすら止まったのを覚えている。
誰もが彼女を見た。息をのむような美しさというやつだ。黒くてまっすぐな髪。光を吸い込むような瞳。ただの高校生とは思えない、異様な静けさをまとっていた。
でも俺は、最初から違和感を覚えていた。
俺の家は小さな神社で、子どもの頃から「神の気配」だとか「人ならざるもの」を感じることがある。迷信みたいな話だけど、うちの神社の名前を出すとたいていの人は信じてくれる。この町限定の話だけどね。
悠木さんからはまさに普通じゃない気配がした。
どうしても気になってしまって、最初に話しかけたのは昼休みだった。
クラスの男子はみんなソワソワしていたが、誰も近づけなかった。見た目がきれいだからとかそういうこともあるかもしれないが、本当はあの異様な空気に圧倒されていたんだと思う。
「お弁当、食べないの?」
俺が声をかけると、悠木さんは少し驚いたように顔を上げた。そして、静かに笑った。
「――食べ方が、わからなくて」
冗談だと思って笑い返したけど、彼女は本当に箸の持ち方を知らなかった。フォークのように突き刺して食べようとしていた。
「もしかして、外国の出身?」
「ええ。ちょっと遠くから」
どこかぎこちない答え。その遠くの意味が俺には外国とはまったく別の意味に聞こえた。
それから数日後の夜だった。
神社の境内を掃除していると、鳥居の向こうに人影が立っていた。白いワンピース。月の光に溶けるような姿。悠木さんだった。
「こんな時間にどうしたの?」
俺が近づくと、彼女はゆっくりと振り返った。笑っているのに、目は笑っていなかった。
「この場所、好きなの。静かで、星が近いから」
彼女は夜空を見上げて言った。星が近い——その言葉の響きが妙に現実離れして聞こえた。
「ここには神様がいるからね。地球は長いの?」
「ううん。まだ……百時間くらい」
鎌をかけたつもりだったが、彼女はあっさりと答えた。
「――地球には何をしに?」
風が止まった。鈴の音が遠くで鳴った。神社が――神様が彼女を拒否している様子はない。彼女は邪なものではないらしい。
「ねえ、君の家って、この神社なんでしょ?」
「うん」
「だったら感じる? この星、壊れかけてるって」
彼女の声が、まるでラジオのノイズみたいにかすれて聞こえた。
「壊れかけて……?」
「ううん。ごめん。気にしないで」
その夜、夢を見た。
空の上から、青い球体を見下ろしている夢。その表面にはひび割れのような光が走り、そこから黒い煙が吹き出していた。
目を覚ますと、外はまだ暗い。縁側の方から小さな光が漏れているのに気づいた。
庭に出ると、悠木さんがいた。両手を空にかざし、指先から青白い光を放っていた。光はゆっくりと夜空へ登っていき、消えた。
「……何をしてるの」
悠木さんは少しだけ驚いたようにこちらを振り返った。
「観測してるの。この星の呼吸を」
「呼吸?」
「人が多すぎて、息苦しそうだから」
その声は穏やかだった。けれど、その奥に、どこか決意のようなものが感じられた。
「悠木さん、君……人間じゃないよね? どうしてここに来たの?」
少しの沈黙。そして、彼女は笑った。その笑いは寂しそうで、どこか安心したようでもあった。
翌日、彼女は学校に来なかった。担任は「転校した」とだけ告げた。あまりに急でクラスは騒然となったが、俺はまだ彼女が地球にいるような気がしていた。
俺は夜、また昨夜と同じ場所に行った。鳥居の下で待っていると、やはり彼女が現れた。
「たったの百と二十四時間で地球を出て行くのか」
「ええ。任務は終わったから。今夜が最後」
「任務?」
「この星を測ること。まだ少し――大丈夫、かな?」
彼女は空を見上げた。まるでそこに故郷が見えるみたいに。
「侵略するんじゃないのか」
冗談めかして言ってみたが、彼女は真顔で答える。
「侵略って言葉、あなたたちの言葉だね。私たちの言葉では、補正って言うの」
「補正?」
「星が壊れる前に、少しずつ直すの。時々、余分なものを減らす」
その余分という言葉に、背筋が冷たくなった。
「……余分には人間も入る?」
「そう。そういうこともある。星がひとつ壊れるといろんなところに影響が出るから」
「だったら、君は——」
「大丈夫。私は人間を残しておく方がいいと感じたから」
彼女は俺の頬に触れた。冷たくて、それでいて優しい手だった。
「あなた、私の光を見たでしょ。だから覚えてて。星が壊れそうなことを」
そう言うと、彼女の体が淡く光り始めた。月明かりに溶けるように、少しずつ輪郭が薄れていく。
「悠木さん!」
手を伸ばしたが、もう届かなかった。彼女は笑って、最後にこう言った。
「この星、もう少しの間は大丈夫。人間もね」
そして、夜空に溶けた。
それから数年。
彼女のことを覚えているのは、たぶん俺だけだ。
ただ、不思議なことがある。あの年を境に、この町では異常気象が減った。地震も台風も少なくなった。星が前よりも少し近く感じられるようになった。
たまに夜空を見上げると、ひときわ強く光る星がある。それを見るたびに、思うんだ。
——悠木さんは、今もきっとどこかの星を測っている。

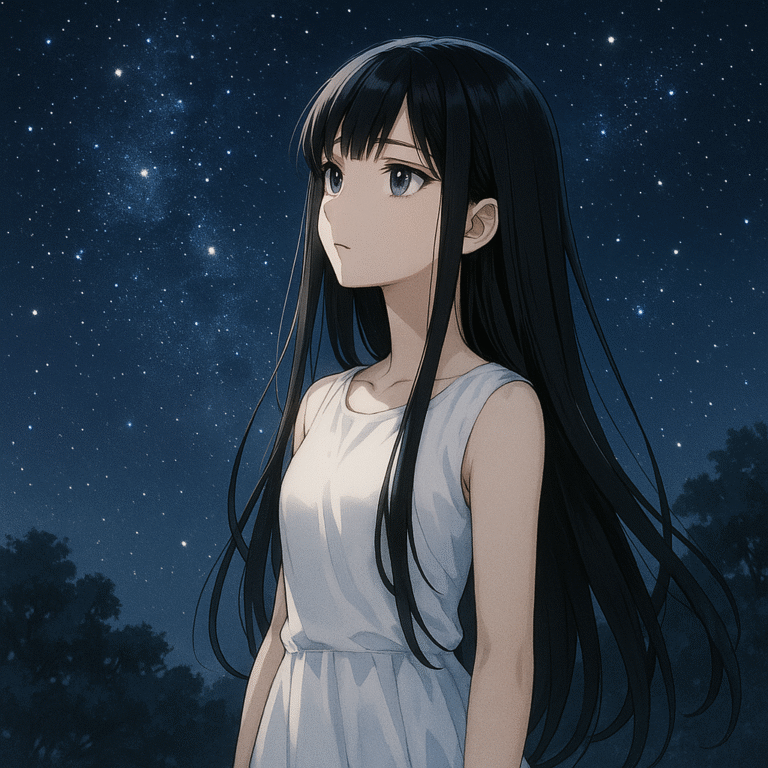
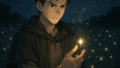

コメント