その話を誰にしても、みんな笑って信じちゃくれないんだ。でも俺にとっては、あれは確かに起きたことなんだよ。
最初の夜は、ただ眠れなかっただけだった。蒸し暑くて、枕の中までじっとりしててな。寝返りばかり打ってるうちに、気づいたら真夜中になってた。
時計を見ると午前二時。テレビをつけても、通販番組しかやっていない。仕方ないから、昔聞いた「羊を数えると眠れる」ってやつを試してみたんだ。
「羊が一匹、羊が二匹」
最初のうちは、馬鹿みたいに思えて笑いそうになったよ。でも、十匹を超えたあたりから、不思議な感覚がしてきた。まぶたの裏に、本当に羊が見えるんだ。真っ白い毛並み、丸い体、柔らかそうな足音。ふわりと柵を飛び越えて、草を踏んで消えていく。
「羊が三十匹、羊が三十一匹」
数えるほどに、体が沈んでいく感じがした。ああ、これは眠れるかもしれない――そう思った瞬間、目が覚めた。……いや、起きたというより、目を開けたら夜だった。
感覚的には朝になっているはずなのに、空はまだ暗いままだった。時計を見ると、午前二時のまま針が止まっている。
妙だと思いながらも、また布団に潜った。けれど眠気は戻ってこない。仕方なく、また羊を数えた。
「羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹」
今度は、羊の群れがはっきり目の前に見えた。俺の部屋の中を、羊たちが静かに歩いていく。どれも真っ白で、目だけがやけに黒い。その瞳が、どこか悲しそうだ。
数が増えるたび、部屋の空気が少しずつ冷たくなっていった。十匹を超えたころには、息が白くなっていた。窓の外を見ても、暗闇しかない。遠くで、何かの鳴き声を聞いた気がした。
「羊が二十匹、羊が三十匹」
いつの間にか、床に白い毛が落ちている。触ると少し温度を感じた。……その瞬間、俺ははっきり悟った。あれは毛じゃない、夜の切れ端だ。
羊を数えるたびに、夜が増えていくんだ。
馬鹿げてるだろ? でも本当にそうなんだ。三十一匹を数えたころには、外の景色が完全に消えていた。窓を開けても、真っ黒いもやのような空気しか見えない。遠くに街灯があるはずなのに、何も光らない。夜が増えすぎたんだ。そして白い羊は、いつの間にか黒い羊になっていた。
俺は怖くなって、もう数えるのをやめようとした。でも、耳の奥で声がしたんだ。
「つづけて」
かすれた、やさしい声だった。女でも男でもない、どこか遠い声。
「まだ、眠れていないでしょ。もっと夜を増やさないと」
その声に導かれるように、俺はまた口を動かしていた。
「羊が三十二匹、羊が三十三匹……」
羊たちは静かに増え、部屋を埋め尽くした。毛が光を吸い込むように、周りがますます暗くなる。やがて窓も、壁も、天井も消えた。
そこにあるのは、羊と俺だけ。
俺はもう、何匹目を数えているのかわからなかった。呼吸するたび、吐く息が夜の色をしていた。時計の針は止まったままだ。
「もうやめたい」と思っても、口が勝手に動く。「羊が……」そのたびに、空気がざわめく。黒い毛並みが擦れ合い、低い鳴き声が響く。
暗闇の中で、ひときわ大きな影が立ち上がった。他の羊よりもずっと大きく、目が赤く光っている。
その羊が、ゆっくりと俺のほうに顔を近づけてきた。鼻息が冷たく、夜そのものみたいだった。
そして、小さな声で言ったんだ。
「あなた、まだ眠れないのね」
俺は声が出なかった。羊は続けた。
「眠れない人がいるたび、羊を数えるたび、夜は増えるの。数を重ねるほど、世界は眠れなくなっていく。だからお願い、もう、数えてはだめ」
そう言って、羊は目を閉じた。その体がふっと崩れ、黒い霧になって消えた。
次の瞬間、朝の光が差し込んだ。カーテンの隙間から、まぶしい太陽の光。時計の針は午前七時を指していた。
俺はベッドの上で、汗びっしょりになっていた。部屋には何も残っていない。ただ、床に黒い糸のようなものが一筋だけ落ちていた。
拾い上げると、それは朝日に吸いこまれるように消えた。
それからというもの、俺はもう羊を数えない。眠れない夜があっても、数えようとは思わない。だって、あれは夜を増やす呪いだから。
……でもね、時々ふと思うんだ。街の灯りが妙に少ない夜、空がどこまでも黒い夜。あれは、誰かがどこかで羊を数えてるんじゃないかって。
もしかしたら、そのたびに、夜がまた一つ増えているのかもしれない。
そして、俺が眠れない理由も、その増えた夜の中に、まだ数え残された羊がいるからなんだろうなって。
今夜も何だか誰かが数えている気がするんだよ。ほら、聞こえる。かすかに。
――羊が一匹。



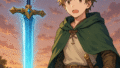
コメント