あの傘を拾ったのは、数年前のことだ。梅雨の終わりの午後で、空はどんより曇っていた。駅前のベンチに、ひとつだけ忘れ物の傘が立てかけてあったんだ。
深い藍色の傘。
閉じた状態でも、どこか濡れているように見えた。俺はどうしても気になってしまってそれを手に取った。そして、そのまま差して帰ってしまった。
泥棒と言われても仕方ないけれど、そのときはそうするのが、自然で当たり前のことのように感じていた。
でも、その日の帰り道、ふと気づいたんだ。傘の表面に落ちる雨粒が、はっきりと形を持っていた。
ただの丸い滴じゃない。
ひとつひとつが、まるで筆で描かれた文字のように並んでいた。それが、言葉になっていたんだ。
最初に読めたのは「おつかれさま」だった。
あまりに自然に浮かび上がったから、見間違いかと思った。でも次の瞬間、雨粒がすっと広がって、別の言葉に変わった。
「ひとりで歩くのは、さみしいね」
足が止まった。
傘の内側は青白い光に照らされていて、周りの景色が少し違って見えた。道路の水たまりも、信号の色も、まるで絵の具を流したみたいに柔らかい。
不思議なのは、傘の外では普通に雨が降っているのに、その傘の中だけは、まるで別の、藍色の空の下にいるような気がしたことだった。
次の日も、傘を持って出かけた。雨が降ると、また言葉が現れた。
「今日のあなたは、静かな顔をしてる」
「見てごらん、道端の花が笑ってる」
「そのポケットの中に、想い出があるね」
そんなふうに、傘は俺に話しかけてくるように言葉を並べた。どれも短い詩のような言葉で、読むと胸の奥がじんとした。
仕事の疲れも、家の孤独も、その言葉を読むと少しだけ和らいだ。
不思議と、傘の下にいる間は誰にも会いたいと思わなかった。誰かと話すより、その言葉を読むほうが落ち着いた。
ある夜、会社帰りに大雨が降った。
雷が鳴って、道が川みたいに光っていた。傘を広げると、雨粒はいつもより激しく降り注いだ。そのぶん、文字もたくさん浮かんでいた。
「ひとりで泣く夜もある」
「でも、空は見ている」
「あなたの歩いた跡が、ちゃんと残っている」
胸がいっぱいになって、立ち止まった。こんな優しい言葉を、誰がくれるというんだろう。人でもなく、神様でもない。この傘の中だけで、誰かが俺を見守ってくれている。
ふと、通りの向こうにもう一人、同じような傘をさした人がいた。
紺色ではなく真っ白な傘だ。色は違うのに、なぜか「同じだ」と感じた。彼女はこっちを見ていた。
風に押されるように近づいていくと、その人の傘の表面にも、雨の文字が浮かんでいた。
でも、そこに書かれていたのは、俺の傘とまるで違う言葉だった。
「ずっと探していた」
「ようやく見つけた」
俺は一歩近づいた。
その人は目元がやさしげな女性だった。
「……その傘、もしかして」
声が震えていた。彼女はうなずいた。
「あなたの傘は詩をうたうのね」
聞けば、彼女も昔、同じ駅前で傘を拾ったという。ただし、それは「対の傘」だったらしい。二本で一組。片方が言葉を贈り、もう片方が言葉を受け取る。俺の傘は受け取る側だった。そして、彼女の傘は贈る側。
「あなたが読んでいた言葉、私が送っていたの。傘が、さみしそうな人の姿を映すから、つい声をかけてしまった」
一瞬、息が止まった。雨の音が遠のいた。
「でも、どうしてそんなことが」
「この傘の下ではね、空が別なの。だから、同じ空を見ていても、違う世界で出会える」
彼女の声が、雨に溶けるように消えていった。気づくと、彼女はもういなかった。そこには、白い傘だけが落ちていた。
その傘を拾おうとしたとき、俺の傘が強い光を放った。雨の粒が一斉に文字になり、空いっぱいに散った。
「これで、ふたりの空はひとつになった」
そう書かれていた。
次の瞬間、雨がやんだ。
傘を閉じると、藍色の表面はすっかり乾いていた。
それから、もうどんなに雨が降っても、あの文字は現れない。でも、不思議と寂しくはなかった。
あの夜から、俺の見る空はどこか柔らかい。傘を持たずに歩いても、雨粒はまるで言葉みたいに頬をなでていく。
時々、空の隅に白い影が見えることがある。まるで、誰かが向こうの空から詩を投げかけているみたいに。
そういうときは、心の中でそっとつぶやくんだ。
――聞こえてるよ。
そう言うと、ほんの一瞬だけ、空が藍色に光るんだ。まるで、あの傘の下だけに広がっていた別の空が、今も少しだけ残っているみたいに――


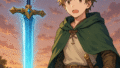

コメント