朝起きて、顔を洗おうとしたら、鏡の中に街が映っていた。
最初は、まだ寝ぼけているんだろうと思って、たいして気に留めなかった。だが、しばらく経ってからまた見てみると、そこにまだ街がある。
小さな家々が立ち並び、塔のような建物の上で風車が回っている。人が歩いている。馬に似た動物が荷車を引いている。
そして、鏡の端から、誰かがこっちを見ていた。
「……なんだ、これ?」
近づくと、鏡の中の空気がゆらりと揺れた。その瞬間、目が合った。
向こうの世界の誰かが、確かに俺を見ていた。金色の髪、真っ白な服。まるで絵本の登場人物のようだった。
俺は思わず声を出した。
「おい、君……」
しかし返事はない。
ただ、その人影は手を伸ばしてきた。鏡の内側から。一瞬、冷たい風が部屋に吹き抜けた。
気がつけば、鏡の表面に波紋が広がっていた。
翌朝になっても、鏡の中の街は消えなかった。
試しに友人を呼んで見せてみたが、彼にはただの鏡にしか見えないという。
「お前、寝不足じゃないのか?」
笑われて終わった。
でも確かに見える。俺には、毎日少しずつ街の様子が変わって見える。
子どもが遊び、店が開き、鐘が鳴る。まるで本当に人々が鏡の中で暮らしているかのように見える。
そして、鏡の中の女が、また俺の方を見た。今度は口が動いた。
「……こちらへ」
声は聞こえない。だが、口の形が確かにそう言っていた。
気づけば俺は、鏡に手を伸ばしていた。指先が冷たい水に触れたような感覚。そして、抵抗もなく、そのまま鏡の中に沈んだ。
次の瞬間、目の前に広がったのは、あの街だった。
青空が広がり、風車がゆっくり回っている。遠くで鐘の音が響く。
本当に――鏡の中に入ってしまったのだ。
女がほほえみ、言った。
「ようこそ、こちら側へ」
彼女の声は澄んでいて、どこか懐かしかった。
女は自らを「鏡王(きょうおう)」と名乗った。この世界は、現実世界の反射でできているのだという。
俺たちが現実で笑えば、この世界でも誰かが笑う。俺たちが壊せば、この世界でも何かが崩れる。
「だから、あなたたちがこちらに来ることは、本来、禁じられているの」
「じゃあ、なんで俺を?」
女は少しだけ目を伏せた。
「あなたの世界で信じる人が減っているでしょう?」
「信じる人?」
「他の言い方をすると、別の世界を許容する人たち」
確かに、最近、科学の発展が目覚ましく、オカルトやスピリチュアルはただの趣味だったり、ときには嘲笑の対象になっている。
「人が私たちを信じなければ、この世界は消えるの」
女は指先で鏡のような泉を撫でた。波紋が広がり、そこに見慣れた自分の部屋が映った。
「この街は、あなたたちの夢見たものの残り香でできている。あなたたちが他の世界の存在を夢見ることで、私たちは存在してきたの」
「じゃあ……今は?」
「滅びかけている」
女の目に、わずかな悲しみが浮かんだ。
俺はその日から、街を歩いた。どこを見ても、現実に存在しているかのような街の風景。
道の両脇に並ぶのは、きちんとした存在感のある建物や屋台、人々は活気に溢れており、滅びかけているようには見えなかった。
「私たちはあなたたちの想像の模写」
街の端に行くと、そこは白い霧で覆われていた。霧の向こうから、時々音がする。ガラスが割れるような音。
「あれが、滅びの音よ」
霧の中を覗いた瞬間、俺は見た。無数の手。形の定まらない顔。鏡が割れたとき、そこにいた者たちが行き場を失って漂っているという。
「彼らは、もう誰にも見られない人。影の影」
鏡王はそう言った。
「あなたがこの街を見たこと、こちら側に来られたことは偶然じゃない。あなたはまだ許容する人だから」
「どうすれば助けられるの?」
「簡単なことよ。たまに私たちを思い出して」
気づくと、俺は自分の部屋にいた。鏡の中には、もう街は映っていない。
ただの鏡。ただの俺。
でも、俺には確かにあの街の風の匂いが残っていた。
それから数週間、俺は毎朝、鏡を覗くようになった。映るのは変わらず自分の顔だけだが、ときどき小さな光がちらつく。
――まだ、滅びてはいない。そう思った。
ある朝、出勤前に鏡を覗いたら、端に小さな指跡があった。誰かが中から触れたような跡。そしてその下に、小さな文字が浮かんでいた。
『ありがとう。あなたのおかげで、まだ光がある』
俺は笑って、鏡を軽く叩いた。
「こっちもまだ、ちゃんと見てるよ」
その瞬間、鏡の奥で何かが光った気がした。たぶん、あの街の朝日だ。

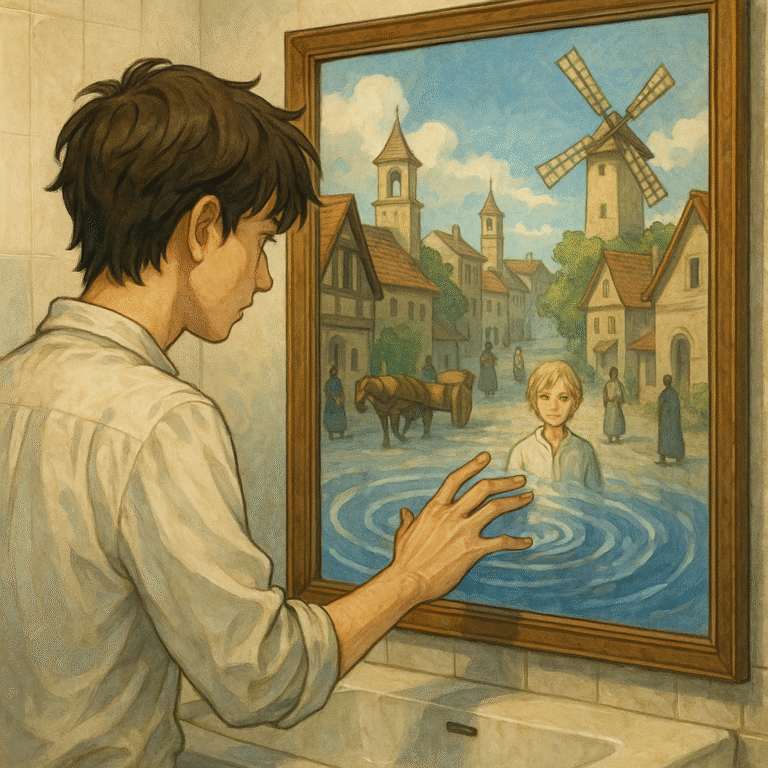
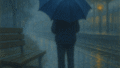

コメント