駅へと続く細い道を歩いていると、道端に潰れかけたペットボトルが転がっていた。
普段なら気にも留めないけれど、その日はなぜか、そのボトルがやけに輝いて見えたのだ。
妙に気になって、拾い上げてみる。
ペットボトルの中を覗くと、小さな光が揺れていた。
驚いて目を凝らすと、羽の生えた小さな人型の生き物が、中で懸命に出口を探して飛び回っているのだ。
「うそ……これ、妖精?」
僕の声に気づいたのか、妖精はくるりとこちらを振り向いて、小さな手でペットボトルを内側から叩いた。
フタを外してやると、妖精は勢いよく飛び出し、僕の目の前をぐるぐると旋回したあと、ほっとしたように肩に止まった。
「ありがとう。あやうく消えるところだったよ」
小さく透き通った声が耳元でささやく。
「どうしてあんなところにいたの?」
「人間の世界は油断するとすぐこんなことになるんだ。いつも誰かが落としたゴミやら何やらに閉じ込められてしまう」
ゴミが落ちていることは確かによくあるが、なぜ中に入ってしまうんだろう。不思議に思っている僕を置き去りに、妖精は肩をすくめた。それから「やれやれ」というように小さなため息をつく。
「これは決まりだからそうするんだけど、助けてくれたお礼。何か願いごとはある?」
こんなに小さな存在なのに、声は妙にはっきりしていて、生意気な雰囲気すら漂っている。勝手にゴミに入ってしまう妖精の間では助けてもらったら願い事を聞いてあげる決まり事があるらしい。
しかし、妖精に願いを叶えてもらえるチャンスなんて滅多にない。けれど、いざとなると、突然すぎて戸惑ってしまう。日頃からこういうことがあったら何を願うのか考えておくべきだった。
「あ、えっと……お金持ち、とか?」
咄嗟に冗談半分でそう言うと、妖精は呆れたように僕の耳を引っ張った。
「つまらない! 本当に人間ってそればっかり。妖精だって飽き飽きしてるんだよ、金だの愛だのって」
どうやら何でもかなえてくれるわけではなくて、この妖精の気に入る願いを言わなくてはいけないらしい。
「じゃあ、何だったらかなえてくれるの?」
「ジャッジするからとりあえず言ってみて」
願いを叶えてもらうのもなかなか面倒くさい。
「あ、そうだ。僕がきみの願いをひとつ叶えるというのはどう?」
妖精は渋面をつくる。
「はぁ? 何いってんの?」
「いや、だってさ。きみのお眼鏡にかなうお願いごとを考えるのも面倒だから、逆に僕が叶えてあげようって――」
「はぁ?」
妖精はかぶせるように声をあげる。
「人間ごときが、何ができるって?」
「そりゃ、できることは限られているけど。できる範囲でがんばるよ」
「ふぅーん」
妖精は僕を値踏みするように、頭の周りを飛び回る。
「本当に?」
戸惑いつつ、僕は頷いた。
「いいよ。きみの願いを教えて」
妖精はしばらく黙ったあと、ゆっくり言った。
「一度でいいから人間になってみたい。たった一日でいい、人間になって、普通に道を歩いたり、カフェでお茶を飲んだりしてみたい」
意外だった。人間のことは小馬鹿にしているとばかり思っていたが。
「素敵な願い事だと思うけど、僕には――」
「わーかってるって! 自分で人間のフリをするくらい簡単なんだよ。――ただ、それには人間がそれを願ってるっていう状況が必要なんだ」
僕はそっと頷いた。
「なるほど。じゃあ、僕の願いは、人間になったきみと一日デートをすること」
僕は街のカフェで、人間になった妖精とコーヒーを飲んだ。それから映画館に行って、一番大きなポップコーンを抱えて映画を見た。最後におしゃれな店が立ち並ぶ通りを歩く。僕は妖精が雑貨屋の巨大なオブジェに釘付けになっている隙に、透明なペットボトル型のブローチを買って、プレゼントした。
妖精は「嫌味なやつ!」と、怒っていたが、気に入ってはくれたようで、胸元につけてくるりと回った。
夕暮れが訪れるころ、妖精は静かに小さな光に戻り、あっさりどこかへと消えてしまった。
その後、ペットボトルが道端に転がっているのを見るたび、僕はなんとなく胸が温かくなってしまうのだった。



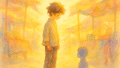
コメント