「まるで自分の影とだけ話しているみたいだった」
市でよく見かける女は、彼をそう表現した。
レアという名の少年が風の市に現れたのは、南の草原に乾いた季節風が吹きはじめる頃だった。市といっても常設の町ではない。風が止んだときだけ開かれる移動市で、誰が主催しているのかも分からない。だが、その市には風に選ばれた者だけがたどり着けるという古い噂があった。
レアは、ほとんど何も語らなかった。問いかけられても、小さく首を振るか、紙に少しだけ何かを書く。けれど、その目は澄んでいて、何かを見据えていた。
「あの子、売るためじゃなくて、何かを買うために来たのよ」
骨董屋の婆がそう言った。確かに、彼は毎回風に選ばれるわりに店をかまえることもせず、市を隅から隅まで歩いて過ごしていた。何かが自分に語りかけるのを待っているようだった。
風の市には奇妙なものが売られている。
「三日前の夢」、「一度だけ過去に戻れる鍵」、「存在しなかった記憶」
レアが足を止めたのは、名もない屋台だった。そこには「無音の手紙」と書かれた箱がひとつだけ置かれていた。
「これは、声を持たぬ者だけが読める手紙だ」と、店主は言った。
レアはゆっくりと箱に手を伸ばし、ふたを開けた。中には何もなかった――と思った瞬間、彼の目に光が宿った。
何も書かれていないはずの紙が、彼の瞳の奥でだけ、確かな言葉を持っていた。
「よく来たね、レア」
その言葉は、レアの中にだけ響いた。
それは、かつて彼が唯一、心を開いていた兄の声だった。もうずっと前に消えてしまった、静かな兄。何もかもを奪われた日、レアは声を手放した。誰にも届かないなら、最初から何も発さないと決めたのだ。
だが、手紙は続いていた。
「お前の沈黙は、世界を拒むためではなく、世界を信じたからこそなんだ。だから、お前は選ばれた。風に。そしてこの手紙に」
その夜、風の市は静かに消えた。
翌朝、レアの姿も消えていた。けれど、彼が立っていた場所には、一通の手紙が落ちていた。
誰にも読めないその手紙は、ただ微かに香る風の中で、確かに、こう囁いていた。
「自分を信じ、少しずつ積み重ねた者は、最後にはきっと風のように自由になる」
それは、誰かの未来へ向けた、優しい祈りのような言葉だった。


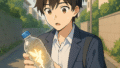
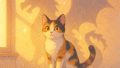
コメント